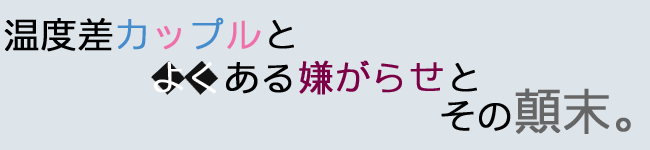フレンの部屋に到着した途端、はフレンのシャツを持たされて、「サイズ合わないと思うけど、代わりの服が届くまでしばらくそれを着ていてくれるかい?」と備え付けの浴室に押し込まれた。確かに、上から下まで泥まみれの格好でいるのは正直気持ち悪いので、はフレンの厚意に甘えることにした。 身体を清める間、濡れた下着は天才魔道士が最近開発したという空調機械にあてて乾かしておいたのだが、残念なことに下は乾いていたけれど上は無理そうだったので、ブラを付けるのは諦めた。 「お風呂ありがとう」 浴室を出て、マグカップを用意していたフレン―――既に騎士の装甲をといた私服姿だった―――に声を掛けると、こちらを振り返った彼は目を見開いて一瞬身体を強張らせた。その顔色はトマト並みに真っ赤に染まっており、は思わず「あー」と、自分の身体を見下ろす。フレンから借りたシャツはの上半身をすっぽりと覆ってはいたけれど、丈はそう長くない。精々太ももの半ばまでをそれなりに隠す程度だ。この格好のままじゃ、自分はともかくフレンが集中出来ず、話なんてもっての外になる気がしたので、 「……ごめん、ブランケット借りれる?」 「えっ、あ、すまない、待っててくれ! ……ああもう、自分のチョイスが間違ってないけど間違ってた……」 そそくさと浴室の扉の影に隠れて待っていると、こちらを見ようとしないまま何事かをぶつぶつ呟き近づいてきたフレンにブランケットを手渡される。 受け取って手早く巻きスカートのように腰に巻きつけると、ようやく人心地がついたような気がして、はほぅと息を吐き出した。フレンも同じだったらしく、まだ頬をほんのりと上気させたままではあるが、に視線を向けてぎこちなく微笑んでいた。ここに座って、と寝台横の椅子にを促し、彼自身は寝台に腰を下ろす。フレンが淹れてくれた紅茶を一口すすって、はフレンを伺った。 安堵なのか落胆なのかわからないが、とにかく深々と息をつくフレンが、の視線に気付いて微かに身を硬くする。それからしばしの間、何かを迷ったように青い瞳を彷徨わせて、最後にに視線を戻して小さく笑った。 「本当はもっと早くに助けたかった。……君が被害にあってるっていう情報は掴んでいたからね。ただ、中途半端なところで釘を刺しても、やり方を変えて続くだけだというのも知ってたんだ」 「……その口ぶりだと、私相手が初めてって事じゃないんだね」 「うん、……常習犯だった。挙句、物的証拠の隠滅も、僕が言うのもなんだけど見事でね。うまいこと現行犯で決めないといたちごっこになるのは目に見えていたから、ここ数回、君が王城に上がるときは地味に厳戒態勢だったんだよ」 「え、えぇぇ」 そんな大げさな、と顔をしかめたが、フレンは首を振って大真面目に続けた。 「―――実は、この数年、王城の関係者……城に勤めていた若い女性が行方不明になる事件が続いていたんだ。……最初はマルガレータ嬢と直接繋がるような事件ではなかったんだけれどね」 どうやらあのご令嬢は、過去、気に入らない侍女や女官を相当数辞職に追い込んでいたという。かなりの歴史を誇る大貴族の家系ゆえに、権力をかさにやりたい放題……とまではいかないものの、そこそこ好き勝手にやらかしていたそうだ。挙句ハインシュタッドの家ぐるみで人身売買にまで手を染めていたらしい。 「最初のうちは、単にご令嬢が気に食わない相手を辞めさせただけだったみたいだけど、父親の方がその嫌がらせを上手いこと利用してしまった。辞職に追い込まれた女性たちを攫って、……娼館や一部の貴族に奴隷として売り払っていたらしいんだ」 奴隷、の部分に嫌悪感をたっぷりと含ませて、吐き捨てる。 「数年かけて逃げられないように慎重に調査して、今朝方ようやく逮捕に踏み切ったところだった。捕縛してから、家宅捜索と並んで取り調べもしたんだけど…………」 苦いものを飲み込むように、ぐ、と口元を引き締め自分の手を見下ろしていたフレンが、そこでをじっと見る。視線の強さには一瞬戸惑いつつ続きを促すように頷いた。 「…………血の気が引いたよ。今日、君を拉致するように指示が出されていたらしい。……そのまま、ハインシュタッド伯爵の寝室に連れて行かれることにも、なっていた」 城に戻ってすぐに彼らに買収された騎士五名を拘束したけれど、と続けるフレンの顔には間違いなく安堵の色が濃かった。もしかして、結構ぎりぎりのところだったのかもしれない、と事の顛末を聞かされながらようやく気付いたの手が、遅ればせながらやってきた恐怖で小刻みに震え始める。 そういえば衝撃のあまり聞き流してしまったが、ご令嬢はこうも言っていなかったか。 (―――お父様ったらこんな女のどこが気に入ったのかしらね、売る前に味見とか言い出すし―――) そうだ。言っていた。味見って何か、なんて決まっている。言いたくもない、女という生き物を侮辱する行為そのものだろう。 もし、フレンが助けてくれなかったら、下手をしたら今頃拉致されて―――、そこまで考えてしまったはぞっとする。手の震えが、嫌悪感をのせてよりいっそう強くなった。 マグカップを、中身を零さないよう慎重にテーブルに戻すと、それを待っていたかのようにフレンの両手がの震える手をそっととって。それから、確かめるように強く握り締める。 「…………間に合って、良かった……」 万感の思いをこめて、フレンが息をついた。手から伝わってくるフレンの熱が、カタカタ震えっぱなしのの手を優しく落ち着かせてくれた。ただそれだけでどうしようもなくほっとして、涙腺が緩む。 「……すぐに言わなくて、ごめんなさい。助けてくれて有難う」 泣きそうになりながら、はやっとそれだけを言う。大事な大事な、謝罪と感謝を。じわりと情けなく滲む涙をどうにかして誤魔化したいが、その手段となり得る両手はフレンの手で柔らかく拘束されたままだ。そうでなくても、若干涙声に聞こえてしまっているから、フレンにはばれていると思う。 そう思っていたら、案の定、フレンの右手がの頬に伸びてきて、濡れた目じりを軽く拭った。ひっそりと笑うような気配をまとったその手が、頬を離れての腰に回される。 「わかってる。君のことだから、僕やエステリーゼ様の為に耐えようとしてくれてたんだろう? ……僕たちを守ってくれて有難う。僕たちのために怒ってくれて、有難う」 その言葉と同時に、今度は身体ごと引き寄せられた。その結果、椅子から立ち上がらされ、金色の頭が自分の胸の高さになったは、フレンの発言に一瞬目を大きく見開いて幼馴染を見下ろした。けれど、エステルを侮辱した言葉を建前に令嬢が確保されたことを思い出して、そういえば聞かれていたのかと思わず赤く染まった顔をそらそうとした。……あれは本心だけれど、本人に聞かれていたとなれば本心だからこそどうにも恥ずかしいのだ。 しかし剣を握ることの多い無骨な手が、それを許さないとばかりに両の頬を包み込む。海の青とも空の青ともつかない色の奥に、熱っぽいものを浮かべながら、フレンが微笑んだ。 「嬉しかったんだ。エステリーゼ様のこともだけど、君が僕の事も守ろうとしてくれたことが、……僕のことを言われて、我慢できなくなるくらいに怒ってくれたことが、凄く、嬉しかった……愛されてるんだって、自惚れてもいいかな」 もとより、二人の想いにどこか温度差があるのはフレンだって気付いていた。そもそも、はあまり感情を表に出すことが得意ではない……というより、周囲に対して少々遠慮がちだ。 だから、きっとがフレンを想うよりフレンがを想う熱のほうがずっとずっと強い、というのが彼や周囲の認識であったから、がフレンに対する侮辱にあれほど怒りを表したのがフレンにとっては結構な衝撃で、相当な喜びだったらしい。 の表情を伺うフレンは、嬉しそうにしながらもどことなく不安気で。フレンの言葉を噛み砕いて理解したは、やがて困ったように笑って。 「……私、誰にでもこんな事出来るほど愛情過多じゃないからね? フレンにしか、したくないし、して欲しくないからね」 そっと顔を近づけて、彼の唇にキスをひとつ。それもたった一瞬だったけれど、自分からあまりこういう表現はしないどころか、実はからキスをしたのは初めてだったので顔から火が噴き出しそうなくらいに熱い。それを見られたくなくて、目を見開いて呆然とするフレンの頭を強く胸に抱きこんで、は「はぁあ、」と深く息をついた。恥ずかしい。とてつもなく、非常に、これまでにないほど恥ずかしい。だがとりあえず、これでこのみっともなく赤くなったであろう顔をフレンには見られまい。それに安心する。 だが、は気付いていない。最後の一手をの想定の斜め上の方向に打ってしまった事に。 ―――それに気付いたのは、数秒後。 腕の中の熱が妙に高くなった。それから、何故か、音のない「ぶつり」という音が耳に届いたような気がした。 そこで初めて、は首を傾げ―――二度瞬きした後にざっと青ざめた。 なぜなら、今、は、上の下着を付けていない、のだ。 慌ててフレンを胸から開放するも、既に遅かった。騎士のたくましい腕はの腰と頭の後ろに絡まり、距離が取れない。 「」 かすれた声とともに、先ほどよりもよっぽど熱の篭った青い眼が見つめてきたかと思うと、あっという間に唇を奪われる。最初は押し付けるように何度か、それから少しずつ唇を割られて、舌を吸われる。上あごを舐められる独特の熱が一瞬の思考を鈍らせたが、同時に緩やかに腰を撫で上げるフレンの手を感じて、 「待って、フレン待って」 性急な流れをどうにかしようと息の切れ目にタンマをかけるが、頬を赤らめつつも目を据わらせたフレンは、 「ごめん、正直待てないし待ちたくない」 たった一言での待ったをさっくり黙殺しての首筋に顔をうずめて口付ける。 「っ、そんなっ、ちょ、ここ、お城……!」 「城だけど、この部屋は僕の部屋だし、誰も入ってこないようにしてあるから問題ない」 「いやでも、服届けてもらうって」 「もうあるよ」 「いつの間に!? じゃなくて、まだ昼間だよ! フレン仕事は!?」 「カーテンして暗くすればいいんじゃないかな。それに、ソディア達に伝言頼んだの聞いてただろう?」 「そうだったー……、っじゃな……っ!」 シャツを割られて、胸元に熱が触れ、はびくりと身体を揺らす。胸元に吸い付いたまま、上目遣いでを見つめたフレンが、囁いた。呼気が、くすぐったい。 「わかってるよ。本当にすまないって思ってる……けど、……駄目かな。どうしても、今、が―――」 「…………」 真摯な眼差しの奥に隠しきれないほどの欲と愛情を感じてしまったから、はもう、降参するしかなかった。抵抗に使用していた力を抜いて、フレンに全身を預け、苦笑する。 「……私にもその気にさせた責任あるよね」 「責任はとってもらわないと、困るかな」 お互い、どこか困ったように笑いあって、寝台に沈み込んだ。
|