中庭に面した人気のない回廊は、どこか神聖な空気を漂わせるほどに美しい。そんな、中庭の一角で。
ばしゃん。
泥水をぶちまけられた。
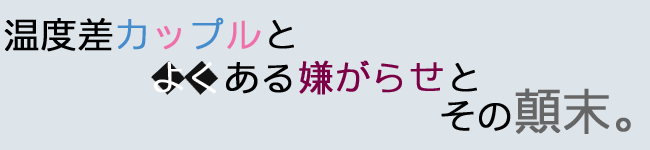
「……」
一張羅の濃紺のコルセットロングスカートにも被害は及び、薄手のシフォンブラウスなどは茶色く濁った水分のせいですっかり下着が透けて見える上に泥まみれだ。礼を失しない程度にうっすら化粧を施した顔やそれなりに気を使ってセットした髪も、水に負けてみるも無残な姿になってしまった。泥が目や口内に入らなかったのは全く不幸中の幸いだった。けれどはそれらに気を払うでもなく、目の前の令嬢……に水をぶちまけた張本人を見つめた。
淡い茶色の見事な巻き毛を揺らし、こちらを忌々しそうに見つめるその目は綺麗な赤。その身にまとうドレスは、が着る服の何倍も上等で豪奢だ。一目で、貴族階級のご令嬢だと知れる。
その白魚のような指には、今さっきに浴びせた泥水が入っていたであろう、それなりに大きなバケツが握られていた。
とうとう、ご本人がお出でになったのか。頭の片隅で、どこか臨戦態勢の自分を認めながら、はつい数週間前の初めての登城の時を思い出していた。
エステルに見立ててもらった、登城用に誂えたロングスカートとシフォンブラウスを身に着けて、エステルの友人として招待されたはザーフィアス城を見上げる。門まで来てくれたなら迎えをよこしますから、とエステルに言われて来たものの、それらしい人影はなく、ただ門番の騎士たちが珍しげにこちらに視線を投げてくるのみ(約束の時間前に来たのだからそれはそれで当たり前だが)。けれど、以前の騎士団の体制のままだったなら、あっという間に不審者扱いされて追い出されていただろう。こんな小さなところで、彼と彼らの努力の結晶が実っているのを見られて、凄く嬉しかった。……その、彼ら、の中に自分も入っていることをすっかり忘れているのはご愛嬌だ。
城門付近の木陰の下で、円環のない青空をのんびり見上げていい天気だなぁ、とふにゃっと笑う。
「!!」
そこに城門のほうから声がかかった。聞き間違えるはずもない、大切な人の声だ。エステルの言っていた迎えって彼か、と何度か目を瞬かせてから、近づいてくる足音に向き直ろうとして、
「わ」
「遅くなったね、すまない」
彼……平民初の帝国騎士団長にして救国の英雄(の一人)、フレン・シーフォに優しく抱きしめられた。門番の騎士二人がぎょっとしているのが雰囲気で何となくわかる。そりゃそうだ、真面目で職務一直線、いかなるときも冷静に、けれど熱く厳しい、多くの騎士たちの憧れとなった若き騎士団長が、砂糖菓子に蜂蜜とメイプルシロップとチョコレートソースをコレでもかとまぶしたような、要するに胸焼けするほど甘ったるい笑顔を浮かべて大事そうにを腕に閉じ込めている姿なんて、見たこともないだろう。彼らの幼なじみとその仲間とか側近の二人とか皇帝陛下とか彼らをよく知る下町の人々でもない限りは、まぁ、ない。
けれど抱きしめられたは、手馴れた様子でフレンの抱擁から抜け出すとふるふると首を振ってみせる。
「待ってないよ、むしろ早く来過ぎちゃった。ごめんね」
それより変じゃないかな、とは自分の姿をフレンに見てもらう。
いくらエステルが見立ててくれたとはいえ、自分のなけなしの貯金をはたいて誂えたものだ。質はどうしたって、貴族のものや上流家庭のそれに比べれば落ちてしまう。姫君の見立てに不安があるわけではないけれど、本当に城に上がっても失礼じゃないだろうか。
そんなの不安を見てとったのか、フレンはそっとの全身を見遣ってから―――砂糖菓子プラスアルファの甘ったるい笑顔を更に深めて、
「大丈夫だよ、すごく似合ってる。……参ったな、誰にも見せたくない」
等と言うものだから、は思わず苦笑した。恋人になった彼は、それまで以上にに対して甘い。甘い上に過保護だ。だからそもそも質問した内容と答えが違っているとか、その感想は随分オーバーだ、と思うけれど、それを言えばその何倍もの勢いで話が長くなるので、敢えて口にはしない。なお、フレンは本気で言っているが、はそれに気付かないし気にしていない。割と温度差の激しい二人である。
とりあえず幼馴染の大げさな賞賛に礼を述べて、それから「仕事中なんだから、抱きしめるとかはナシだからね」と笑いかけると、珍しくも言葉をうぐ、と詰まらせたフレンは、「……確かに。気をつけよう」と小さく肩を落とした。……そうして、ふと、フレンが微かに後方を気にするそぶりを見せる。に気付かれたくはないのだろうが、長年の付き合いから何となく察知してしまった彼女は、ちらりと視線だけを向けた。
城門前の二人を、城門付近の街路樹の陰から覗く女の姿があった。女というには少々年若い、十代後半といったところのその人物は、無言のままを睨みつけていた。
―――その少女が、今に泥水をぶちまけたお嬢様である。
騎士団と評議会。
その対立は、ヨーデル・アルギロス・ヒュラッセインが皇帝に即位したことで一応の決着がついた。けれども、それで全てが綺麗さっぱりというわけもなく、議員を務める貴族の中には、騎士団のトップ=フレンに取り入って裏から牛耳ろうという人間も少なくはない。このご令嬢の父親もその中の一人であるのだが、そんな事実をが知るわけもなく、危機感薄い彼女は、事実は小説より奇なりって本当なんだな、とか正直どうでもいいことを考えながら、目の前のご令嬢を観察していた。
二度目の登城から、度々嫌がらせ染みたものは受けていた。ご丁寧に、仕事に戻ったフレンやエステルと別れて帰宅しようと一人になっている時に。例えば、通路で足を引っ掛けられ、転ばされたとか。あるいは、さざめくような笑いとともに汚いものを見る目を向けられて、「これだから愚民は」とこれ見よがしに言われたとか。他にも色々、この数週間で、王宮を舞台にしたよくある恋愛小説によくある嫌がらせは、多分大体受けたと思う。そしてそのどれもにこのご令嬢の姿がちらついていたので、おそらくは嫌がらせの主犯ないし指示をしたのはこの人なのだろう。
ただ、それとは別に何度か。
自身を値踏みするような視線を感じたことがあった。それは決まって、ちらりと見かけたご令嬢の隣に、妙に丸い中年男性がいる時だ。令嬢と同じ茶色の薄い髪と赤い垂れた目の持ち主に、ねばっこい視線で嘗め回すように見られた時は鳥肌が立った。こういう思いを、城の女性は毎日しているのかもしれないと思うと、姿勢良く城内を歩く侍女達に対して、尊敬の念を抱く程に。
「泥まみれで間の抜けた顔だこと。……汚らわしい。本当、愚かな下民ね貴女」
……貴族って、物凄く素晴らしい人かどうしようもなくこちらを見下してくる人のどちらかしかいないのだろうか、思わずそんなことを考えてしまっただった。
そんな彼女にお構いなしのご令嬢は、せっかくの美しい顔を歪めてを睨み続けている。口元を美しい羽たっぷりの扇で覆い隠しながら、まだまだ言い足りないのかぶつぶつと言葉を連ねていた。
「せっかくこのわたくしが、貴女のような愚民如きが城に上がるなど……挙句姫様のお気に入りだとか、フレン様の幼馴染だとかくだらない触れ込みで玉の輿を狙うなど身の程知らずだと散々教えて差し上げていたのに。わたくしの優しさをすべて無碍にするとは、さすが愚民。愚かしいことこの上ないわ。だからこの度はわたくし手ずから知らしめて差し上げたのよ。泥水のひとつでも浴びたのだから、目を覚ましたのではなくて? ……あーあ、お父様ったらこんな女のどこが気に入ったのかしらね、売る前に味見とか言い出すし……趣味悪いわ」
どうやら、あの数々の嫌がらせはご令嬢の親切心だったようだ。いやはや全く思い至らなかった。むしろあれを優しさだと思い至るとしたら、よっぽどの被虐趣味だと思う。要するに、は呆れた。怒りや悔しさがないわけではないけれど、それ以上に呆れてしまった。なので、最後の聞き捨ててはならない部分をすっかり耳から押し流してしまったし、どういう根性しているのか甚だ疑問に思ったし、今までの仕打ちに文句のひとつだって言いたいと思うけれど、自分より明らかに身分が上のご令嬢に対して余計なこと言ってしまったら、自分に近しいエステルやフレンに対して貴族が攻撃できる材料を与えてしまうかもしれないと思いついて、口をついて出そうになった文句を無理やりかみ殺す。
―――勿論、たったこれだけのことで酷いことになるなんてあり得ない、という気持ちはあるし、事実そんなことにはならない。フレンもエステルも、そしてその二人とともにある皇帝ヨーデルも自分などよりよっぽど心が強い人だ。しょうもない難癖つけられてもさらりと退けられるだろう。
けれど、それでも。
欠片でも、弱みになるかもしれないような振る舞いだけはしたくない。それだけは確かにの中にあって、だからこそは、胸のうちに燻る憤りを堪えながら、努めて無表情を作った。泥にぬれた唇をぎゅ、とかみ締めると、土の味がする。……せっかくエステルが見立ててくれた、フレンが似合うと言ってくれたスカートもシフォンブラウスもほぼ駄目になるだろう。それだけが残念だ。
は、今までの嫌がらせの件をエステルにもフレンにも告げていなかったし、知られてもいなかった。相手も相手で、なるべく人の目がないところを狙ってきていたのが幸いして、これまで嫌がらせの現場を目撃されたことはなかった。……よかったと、心底思う。少なくとも、今この場を何事もなく切り抜けられればの勝ちだ。こんな理不尽な扱いを受けるのは自分だけで充分なのだから。
けれど、ご令嬢の一言がが我慢していた感情にヒビを入れた。
「まったく、姫様もフレン様も頭がおかしいのよ。こんな品のない下民の女を友人だと扱って。フレン様も所詮は下民だわね。このわたくしが栄えある帝国騎士団長という身分に免じて嫁いで差し上げてもいいと言っているのにこんな女ばかりを気にかけるなんて、麗しい見た目と違って脳みそは筋肉なのかしら。それならそれで御しやすいけれど。……姫様も姫様よ、頭の中お花畑でいらっしゃるのね。本当、鈍くさいだけの馬鹿姫が副帝なんて気が狂いそう―――」
―――ぶつん。
久しぶりに、自分の中の何かが切れた音がした。
2→
|