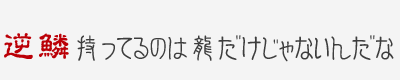荒れる息の合間に、苦しげに呻いた。 「くそ、……ん、な、ところ、で、」 白い着物を左前に着た姿の男は、青ざめた顔でどことも知れない建物の中を走る。裸足のせいで足音は殆しない。 ひたひた、ひたひた。ひた。 時折、太い柱の陰に身を潜めては、追手がないかを確認し、また走りだす。 「こんな、……ところで……!」 男が握るのは、束縛を振りきった矢先にとっさに掴んだ、鬼の持ち物らしきしっかりと研がれた刃物。 「俺は、死なねぇ……ッ」 ―――死んでたまるか。 彼の前を歩く、着物姿の女の背に向かって、亡者の男は乱暴に手を伸ばす――― それが、彼自身にとどめを刺すことになったとは気付かずに。 「うわああああすみませんごめんなさあああい」 「ほっ、本当に申し訳ありません…………!!」 茄子が情けない謝罪を繰り返す横で、唐瓜も一緒に頭を下げた。亡者の脱走を許すという獄卒としてあるまじき失敗に、鬼灯は非常に嫌そうな顔を隠すことなくため息をついた。お怒りである。 「何度目ですか、茄子さん」 ぱしーんぱしーん、手のひらに打ち付ける金棒の音が死刑宣告に聞こえた茄子はひぇぇぇぇと震え上がってもう何も言えない。趣味の方面で才能をいかんなく発揮するこの小鬼は獄卒としてはどうにも抜けていて、しかしどうにも憎めない。茄子を知る大半の獄卒がそう思うとおり、鬼灯にとってもそうだったらしい。 全く仕方ありませんねと独り言ちる鬼灯と、後々の呵責は免れないものの、とりあえずのお許しをもらった新卒二人が深々とため息をついた途端、別の獄卒が飛び込んできた。 「たっ、大変です! 脱走した亡者が、様を人質に…………!!」 ビシリ。ドゴメシャッ。 場の空気が凍った音と鬼灯の金棒が床に突き刺さる音が、唐瓜と茄子の耳にはっきりと聞こえた。 俺、死ぬかもしれない……茄子は色々覚悟したという。 刃物を喉元に当てられた女は、無言で男の腕の中に抱えられていた。 怖がるでもなく、ただまったく常と変わらない(と思われる)顔色で男を見上げるだけで、流石に地獄の女なだけある、などと男はチラリと思う。怖がってくれたほうが都合はいいのだがこの際しょうがない。だが周囲の反応は、 「お、おい、あれ様じゃないか」 「ちょ…………、おいヤバイぞ! どうすんだよあれ!?」 「このままだと……くそ、とと、とにかく連絡!」 といった感じで、鬼どもたちは相当な緊迫状態にあるように見えた。 どうやらこの女は地獄でも立場が上に当たるらしい。そんな重要な女鬼ならゴリ押し出来るかもしれない、そんな期待を抱くに至り、思わず笑いに歪む口を威嚇するように修正しながら、歯を剥いてみせた。 どよめく鬼たちに囲まれつつあるが、一定の距離以上は近づいてこない。これはイケる、間違いない。 そんな確信を胸に秘め、男はあの世と現世の境を目指し、女の首を抱えたままじりじり歩く。 と、その女が、くい、と着物の袖を引いた。 「……あァ?」 「そろそろ、気が済んだでしょう?」 いたずらした子どもを優しく諭すような言い方だった。眉根を寄せ、口を引き結んで男を見るさまは、どこからどう見てもいたずらっ子を叱る母親のようだ。それが非常に気に障る。 「これ以上は洒落になりません。貴方が今後与えられる呵責や、転生までの期間に関わってくるんですよ」 今ならまだ取り返しが効きますから、繋げられた言葉に男はつい女の首を抱える腕に力を込めた。「かは、」と呻き声が女の唇から漏れ、それに気を良くした男はそのまま黙れと更に力を入れる。女の顔が苦しげに歪んで、うっすら土気色を帯びたところで、わずかに腕をゆるめた。こいつらが死ぬかどうかは知らないが、万が一にも殺ってしまうわけにはいかない。殺しはしない、けれど楽にもしない。 周囲がざわめいた。見れば青ざめた鬼どもが―――鬼のくせに青ざめるのかよ、なんて嘲りたくなりつつも男は自分の周りを観察していた―――、いつの間にか二手に分かれて真ん中に道を作っていた。 その道をのしりと歩いてきたのは、黒い着物を着た一本角のガタイがいい鬼の男だ。 その背後に小さい子どもみたいな鬼が二人ついてきている。その小鬼の顔はこれ以上ないくらいに真っ青で、なんて思ったところで、全身にそれはそれは強烈な怖気を感じた。発生源は、目の前の一本角の鬼だ。効果音にしたら「ずもももももも」って感じで男に迫り来るそれは、間違いなく怒りだ。 途端、亡者の男を囲っていた輪がズゾゾ、と音を立てて広がった。その反応に男は動揺した。そして気づく。 全員揃って、こっち見て拝んでることに。えっ、どういうことこれ。男の動揺はさらに強くなった。 そうこうしているうちに、一本角はゆったりと足を進めてくる。だがゆったりしているのは動きだけで、鬼が発する怖気と威圧感はみるみる凶悪になってきていた。 唐瓜は目の前の惨状に目を背けたい気持ちでいっぱいだった。 取り逃がした亡者の男の腕に抱えられているのは、だ。しかもかなり強く首を絞められているらしく、眉根が苦しげに寄っていて、唇はゆがんでいる。「かは、」なんて息もできない様子で、それだけでは飽きたらず、亡者は更に首を強く締め出した。 (そっ、それ以上は頼むからやめとけよぉぉぉぉぉ!! 悪いようにはしない、いや呵責はちゃんとするけど!!) なんて唐瓜の心の叫びが届くわけもなく、男はまるで勝ち誇ったように包囲網を見回している。 気づけ、頼むから。 様が声を上げた瞬間、それを見た鬼灯様が呵責すら生ぬるいって怒気全身で撒き散らかしてるから!! ほら見てみろ、周りの獄卒たちもあまりにもあまりな鬼灯様の状態に仕事忘れて逃げ出したくなってんだから!! 叫び出したいこの気持ち、プライスレス。 などとよくわからない領域に行きかける思考を抱えた唐瓜も、他の獄卒とともに両手を合わせていた。お前のことは一瞬だけ忘れない、と全員思ったかどうかは定かではないが、鬼灯が何も言わずただただ無言で近づく先にいる男の冥福を今更祈るようなものだった。もう死んでいるのに。 と、苦しそうな呻きをあげていたの腕がゆるりと上がった。必死に拝み倒している獄卒と鬼灯に気を取られている亡者は気付かない。するん、と袖から何かが出てきて、それを握った嫋やかな手が、割と勢い良く動いた。 ぷすっ、とちょっと間抜けな音がして、ついで亡者の悲鳴が上がった。おぎゃあああ痛えぇぇぇ、とだみ声で痛がる亡者の腕を軽やかに抜け出てきたの顔には、先ほどまでの苦しさに喘いでいた面影はない。どうやら演技だったようである。うおおー様すげえ、茄子が歓声をあげていた。 「手間を取らせてしまって申し訳ありません鬼灯様、気を引いてくださって助かりました」 亡者の首を刺したもの―――簪を再び袂に仕舞いこみながらぺこりと頭を下げるに、鬼灯は無言で視線を返す。黒目があちこちさまよっていて、あ、これ怪我がないか確認中だ、と唐瓜が気づくのと同時に、鬼灯の目が一段と鋭くなった。どうやら、喉元が少し赤くなっていたらしい。 「…………さん、後で個人的にお話がありますので執務室で待っていて下さい。私はそこの亡者を詳しく調査しますので」 「こ、個人的に、ですか……わかりました、お待ちしています」 ひくっと顔をひきつらせたが了承すると、それに小さく頷いた鬼灯に「唐瓜さん、茄子さん」と呼びかけられた。一緒に執務室へ行くようにとのお達しだ。の後ろをついていく形で、間違いなく叱られてボコボコにされるよなぁという覚悟を決めた様子でとぼとぼ歩く茄子を慰めては諭しながら、
|