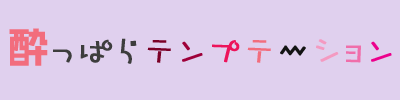「うふふ、ふふふ、ゆーりー」 少し舌っ足らずな呼びかけに、呼ばれた男は呆れと愛おしさを混ぜたかんばせを向けかけて、それとなく目を逸らした。「どーした」と少しぶっきらぼうに尋ねると、幸せそうな笑い声をあげてから、「んーんー、好きー」とあっけらかんと言ってのける。 普段にないの素直さに思わず面映くなりながら、ユーリは「そっか」と鼻の頭を掻いて短く返した。 彼女の部屋は玄関を超えると履き物を履かずとも過ごせるようにと、それなりに上質なラグが敷かれている。曰く、この幼なじみの娘がこつこつと貯金して何とか買い付けたという一品だ。どうやらカウフマンが色々と便宜を図ってくれていたようで、「これくらいはさせてもらいたいわね」とにこやかな笑顔でピシャリと言い切っていた、とが苦笑していたのをみた記憶がある。 そんなふわふわのラグの上に裸足でぺたりと座ったユーリの両足の間に、ユーリと向かい合うように座ったから、ほんのりと甘い果実のにおいがただよっている。さっき夕食の時に出てきたジュース…と勘違いして飲んでしまった果実酒の甘い香りを纏わせて、は猫科の生物よろしくユーリに擦り寄っていた。 酔っ払ってらっしゃるなー。 擦り寄ってくる温もりをそれとなく遠のけつつ、どうしても向いてしまいそうな視線を天井にやりつつ、そして可能な限り意識をここではない遠いところに向けながら、ユーリは事実だけを思う。 ―――うっかり意識を向けたが最後、間違いなく押し倒す。 と、確信する程度、ユーリの理性は揺さぶられていた。 一応は、恋人同士と言う免罪符を手に入れているし、既にキスだけで済む間柄じゃなくなっているのでそれはそれで問題はないのだけれど、何分は酔っ払っている。酔っ払い相手にあれこれやったとして、「覚えてない」の一言を食らったら流石にショックだし。そも、酔っ払っている状態に付け込んでどうこうするのは何となく気が引ける。 とは思うのだが、なんか暑いねぇとふにゃらかしながら胸元のボタンを開けて下着と谷間が見え隠れするような状態のままべったりくっついてくるこの現状、もうそろそろ俺頑張ったよね? と誰でもない誰かへギブアップを申告したくなる程度には、もうどうでもいいような気はしていた。 「ゆーりー?」 疑問符を語尾に貼り付けて、が両腕をユーリの首に巻きつけた。黒髪がの肌を滑ったのか「ふひゃ」と怪しい声をあげる。その怪しさに寝台の中の睦み合いを連想してしまって、勘弁しろよ、とユーリは溜息をつきたくなったけれど、億尾にも出さずぽんぽんと、と二度ほどの頭を叩いた。いい加減にしとけよ、と正気づいてくれることを願って。 けれども何を勘違いしたのかまったく伝わらなかったのか、の酒で赤らんだ頬が緩んだかと思うと、ぎゅう、と抱きついてくる。ユーリの開いた胸元に、がさっき自分で解放した胸元が触れて、彼女の熱とその付近の柔らかさを男に伝えた。 一瞬でその熱が別の形で感染し、ユーリは思わずごくり、と喉を鳴らした。意識の外で両腕がの体を捕まえようと動き、寸でのところで堪える。危なかった、もし抱きしめていたら色々取り返しがつかなくなっていた。―――この状況であまり意識したくはないのだが、正常な男の体は悲しいかな正常に反応してしまい、それを悟られたわけでもないのに何だか気まずくなって顔を赤らめながらじろり、と目を逸らす。 そんなユーリのジレンマに当然気付く訳がないが、やっぱりふにゃふにゃの笑顔のままユーリの首元に顔をすり寄せた。それから何を思ったのか―――ぺろり、と首筋を舐め上げ。 「っ、おま」 首を滑る感触に動揺して思わずを見る。いたずらが成功した子供の顔で笑うの目はとろりと潤み、ユーリの視線を受けて更に蕩けた。 「やぁっと、わたしのこと、みてくれたねぇ」 「だから、……っ」 そのまま、はくはくと空気を食むユーリの唇を塞ぐ。あまりのことに呆然としていたユーリが我に返るまでその間数秒。少し焦れたような表情のが下唇をはむはむと甘く噛み、その刺激でようやく自我を取り戻したユーリだったが、この唐突な酔っ払いのキスが普段自分が仕掛けているやり方と同じだと気付いた直後、言い知れない何かが体の中を貫いて、瀕死の理性に止めを刺す。 侵入してきた果実酒の味が残る舌を自分のそれと夢中で絡めて、「ん、む」と苦しげに呻くにリベンジを果たすと、空気を求めて離れた唇にわざと呼気を当てながら、ユーリは悪い顔を作ってニヤリと笑った。 「酔っ払って誘惑してきたお前が悪い。もう容赦しねえからな?」
|