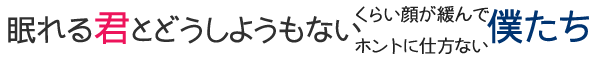久しぶりに見た。 黒い髪と、金髪が、ソファに並んで座って―――転寝なんてしてるところを。 生活する場が分離してからもう数年。 フレンが騎士団の一員として城内で規律ある営みを送っていたのに対して、ユーリは割と悠々自適な生活をしてきた、ように思う。 少なくとも私よりは起きる時間は遅く、就寝する時間も遅かった。だらしないというよりは、夜遅くの揉め事を片付けるのに都合がいい所為だとは思うけど。 ―――そんな二人が、揃って旅をしてある程度生活の時間が重なるようになって、こうやって同じようなタイミングで仮眠を取るようになったのか。何だかいつも一緒だった頃を思い出して私は思わず口元を緩める。 本人達が意識したのかはわからないけれど、二人の間にはちょうど一人分のスペースが空いていた。その隙間に私が入り込んでみれば、幼かった頃の再現が見事に完成した。 懐かしいなぁ、としみじみ思う。 昔はよく三人で一緒くたになって昼寝なんてしたものだ。 まだまだ性別の差異も少なく、多少の体力差はあったけれど二人について色んな無茶をしたっけなぁ。 あの頃からフレンは過保護で、私が怪我をするとすぐ怒ってたな。「女の子なのに怪我ばっかりしてどうするんだ!」なんて。 ユーリは私がやりたいと思ったことをある程度尊重してくれたりして、たまにフレンと喧嘩になってたっけ。フレンが折れるか、私が取り下げるかするまで二人でにらみ合って、ずっとハラハラしていたのを思い出す。……あの頃から、私はずっと二人に大事に守られてきていた。 正直に言ってしまえば、いずれ私は置いていかれるのだろうと思っていた。 私は女で、ユーリとフレンは男性。 そして、守られているだけの私と、私を守りながらも夢を追い求めた二人。 性別以前に根本的な心の強さが全然違う。 いずれ私より大切な存在を見つけ、私のそばから離れていく。そう思っていた。 ―――置いていかれる寂しさは身をもって知っている。 置いていかれるくらいなら置いていってしまおうか、―――何度も思って、ついには実行した。けれど幼馴染達はそんな私の手をしっかりと捕まえ、結局一緒に歩んでくれるのだ。置いていったりしないと、しっかり手を握ってくれる。 ”真っ先に守る対象”からは外れはしたが、まだ一緒にいてもいいと許してくれている気がして、嬉しかった。 かすかに寝息を立てる二人の顔を窺う。 性質の違う、けれど整ったふたつの顔は、眠りに落ちている所為かいつもより幼く見えて、思わずクスリと笑いをこぼす。 眠っている所為で少しずつ姿勢を崩していくフレンの頭を膝に乗せ、ずり落ちかけるユーリの頭に自分の頭をすり寄せながら、見た目よりたくましい肩に寄りかかるようにしつつ支える。 ―――せめてこうしている間だけでも、私を必要として欲しかったから。 今だけはこうしていても、許して欲しかった。 だと言うのに、気づけば二人から体温を分けられて、不思議な安心感に包まれながら私はいつか眠ってしまっていた……――― 「「……………………………………」」 が、ユーリとフレンの間で眠り出してから数十分後。 ほぼ同時に目を覚ました彼らは自分の置かれている状況に一瞬頭が真っ白になった。 ユーリの頬の下、眠るの頭が甘えるようにユーリの肩に重みをかけて寄りかかり、すよすよとやわらかい寝息を立てている。 フレンの頬の下には弾力のある柔らかい太もも、フレンの腕は眠っているうちにその太ももを抱き寄せるように伸びていた。 ((…………これは………………)) そして同時に思った。 起きられない、…………いや起きてしまうのがもったいない。 ユーリは普段甘えるような素振りを見せないが無遠慮にくっついて眠っている事実に顔が緩んでいくのを感じた。の両手が、ソファに力なく落ちていた自分の手に重なるように置かれていて、まるで求められているような錯覚さえ覚える。変な欲がこみ上げてきそうになるのを 「あーもーくっそ、寝てるときだけこんな甘えてくるとか、……っとに可愛すぎんだよお前……」 と、妙にふて腐れた声色で誤魔化して、手の甲で赤くなる頬を押さえ。 呻くように呟いたその内容に対し、微妙に照れくさくなったユーリは所在無げに視線を彷徨わせ、そしての膝の上で両手で顔を押さえながら声もなく身を捩りまくるフレンを見つけた。隠し切れなかったらしい耳はトマトより赤い。というか、悶えているらしいその動きが若干気持ち悪い。 色んな意味でのキャラ崩壊の危機を悟ったユーリが渋々声を掛けると、フレンの動きがぴたりと止まる。 そして僅かに上擦った声で、何かを抑えきれないといった風情で、フレンは呟いた。 「ユーリ……の膝枕が気持ち良過ぎて起きれる気が全くしないよ……どうしたらいいんだろう……」 「…………そーかよ…………」
|