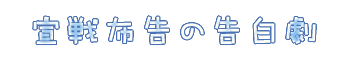「エステリーゼ様、大丈夫ですか」
「はい、平気です」
「あんま無茶しなさんな、フォロー出来損ねたらたまったもんじゃねえ」
前線に出ている三人を眺めながら、私は一人重たい息をついた。
胸の奥にくすぶるチリチリした痛みと嫌な感情を必死に消し去ろうと努力しているのに、消えてくれない。
―――ここまで酷いことになるとは我ながら思いもしなかった。
旅に出るまで―――ううん、少なくともフレンはそれよりももっと前だと思うけど、それまでは二人の庇護対象は私だった。
何か困ったときは二人が必ずといっていいほど手を差し伸べてくれていた。私の生い立ちに同情的だったからとは言え、それ以上を勘違いしそうなくらいに幼なじみ二人は私を守ってくれていた。
でもそうやって私を守ってくれることに、心地よさと同時に申し訳なさも感じていたのだ。
だからこそ、私は当初二人に内緒で旅に出る準備をしたし、こっそりとテムザ山に向かおうとしたわけで(速攻ユーリたちに見つかったけど)。
とにかく、当時の私はフレンのわかりやすい過保護から―――そしてユーリのわかりにくい庇護から卒業したいと願っていたはずなのに、いざそこから離されてしまうと寂しくて堪らないとか、なんとも情けない。
そう、寂しいのだ。
二人の間で一番最優先される筈だった守るべき対象が、私からエステルに移行したことが寂しいのだ。
でもそれは、当たり前だとも思っている。
エステルは今でこそその力を振るうことに危険はないけれど、かつては始祖の隷長に命を狙われ、そして騎士団長だったアレクセイに力を狙われ酷い目にあわされて―――、それでなくても彼女は皇族のお姫様で一時は皇帝候補として扱われていたわけで。
私はと言えば、体に宿った術式のことを必死に秘密にしてきたから、誰にも狙われることもなくのうのうと旅を続けていられたのだし、最近になってようやく戦闘に参加できるようになったけど場数踏んでないから結局後方支援に留まるだけ。その点を顧みても、前線に出て剣を振るうエステルとは比べるべくもない。
そこまで判っているのに、どうしても寂しくて仕方ない。
最近はその感情が酷すぎて、まともに三人を見ることが辛くなってきたくらいだ。
―――というようなことを、私の様子がおかしいと一人連れ出してくれたレイヴンさんに思わずぼそぼそとこぼしていた。
旅のメンバーの一人がここのところずーっと暗い顔をしているから心配して訊ねてみれば、蓋を開けたら幼なじみをとられたと思い込んで寂しがるという―――要するにただの嫉妬、なんていうこんなあほらしいことを聞かされるレイヴンさんに心から謝罪したい。
「で、ちゃんはこの現状が辛い、と」
「はい……でも完全に身勝手な理由なので……」
「まぁ、そうだわなぁ。申し訳ないけど身勝手なことにかわりはないやね」
私の自嘲を容赦なく肯定したレイヴンさんは、どーしたもんかねぇと顎をさすって。
「ちゃん自身は、どうしたい?」
穏やかな声で聞かれて、私はずっと考えていたことを口にする。
「そろそろみんなとお別れしようと思ってます」
「…………そりゃまた何で」
「そもそも私の目的はテムザの町で父を弔うことで目的も済んでるし、それにその、あまり戦えない私が居ても足引っ張りそうだし、これがいい機会だなって思って」
「……してその心は」
「う」
それっぽい理由を見繕ってみても、レイヴンさんに本音を言えとさり気なく諭されて言葉に詰まる。この聡い人相手に誤魔化しきれるはずはなかったな、とため息をついた。
「……身勝手が過ぎて、いつかユーリたちに嫌な事を言ってしまいそうなんですよね、私」
「だから、もう見ないように離れちゃおうって?」
こくりと頷く。一人は辛いんじゃない? と続けるレイヴンさんに
「酷い事言っちゃって嫌われるよりはマシだろうし」
そう答えた、その時だった。
「僕らから離れてどこに行くつもりなんだい?」
「で、誰が誰を嫌うんだって?」
背後からした聞き覚えがありすぎる声にぎくりと体が固まった。目だけを動かしてレイヴンさんを見ると、その顔にはこうなることが判ってたと言わんばかりの苦笑いを刻み込んでいて。ゆったりと立ち上がると、「ま、腹割ってきっちり話し合ったほうがいいわよん」とひらひら手を振って去っていってしまった。
―――そしてこの場に残るは、がっちり私の肩を抱くユーリとしっかり私の背に腕を回すフレンに挟まれて冷や汗が噴出した私の三人。
「つかぬ事をお聞きしますが、二人とも話はどこから聞いていたのかな……」
「俺たちがまもってくれなくて寂しいって凹んでたところから?」
ギシギシ言いそうな首を上向かせながら恐る恐る尋ねると、ニヤニヤ顔のユーリに言われ私は頭を抱えた。も、もう殆ど最初からじゃないか……!!
気まずくてうううとかあああとか言葉にならない呻き声をあげていると、背中に回されたフレンの腕に力が込められて、ほんの少しだけ抱き寄せられる。
と、何故かユーリの腕にも力が入り、僅かに開いたユーリの体との隙間が元に戻る。何事だ、と思ったけれどそこに「」とフレンの声が頭の上から降ってきて意識が戻された。
「それで、僕らと別れたら。君はどうするつもりだったの?」
「あ……」
そう問われて、私はふと思い悩んだ。
―――考えてなかったわけじゃない。
帝都に戻るのもいいかと思ったし、このまま世界を回るのもアリかなとも思っていた。けれど、どちらにしても行き当たりバッタリなことには変わりない。何にせよ、離れることが先決だったから。
答えに窮する私を見て取ったらしいユーリが優しく笑う。
「ま、特にこれといって決めてないんなら、わざわざ別れて一人旅なんてしなくてもいいだろ」
「でも、……聞いてたんでしょ、私自分勝手なんだよ。二人の過保護から逃げだしたかったのにいざ離れたら寂しくて、今守られてるエステルに嫉妬したとか、バカみた」
い、と続くはずの言葉がフレンの掌で口を塞がれてしまう。何するの、と目線で訴えるとフレンはさわやかな笑顔を向けてきた。
「そんなこと言わないで。僕らは……少なくとも僕は嬉しいんだ。君がエステリーゼ様に嫉妬してくれたっていうのが」
「……は?」
緩んだ掌の拘束を抜け出して漏れた音は今の私の混乱を如実に表していた。
私がエステルに嫉妬したのが嬉しいって、何を言ってるのフレンは。
「ま、望んだ方向とはちーっとズレがあるけどな」
続けてユーリもフレンの言葉を肯定し、ますますこんがらがった思考についていけなくなる。
「そのあたりは追々でいいんじゃないかな。焦らせたら今度こそ逃亡しそうだよ、」
「……急かさないと変なところから掻っ攫われそうな気もするけど。恋敵がお前ってだけでもヒヤヒヤモンなのに」
「はは、それは僕の台詞だよユーリ。まぁ……大丈夫、と言い切れないところが怖いね」
「全くだ。色んなところで愛嬌振りまいてるし、いつ男が言い寄ってくるか気が気じゃねぇ」
頭上で交わされる男二人の会話の意味がよくわからない。
いや、わかりそうだけど、動揺のあまりそこまで理解が及んでないというか。
愚かな私は何とか理解しようとフレンの「私がエステルに嫉妬したことが嬉しい」の一言とユーリの「望んだ方向とはズレがある」の言葉を加味してここまで会話を考えて、……………。
いやまさか、そんな。
それはちょっと自意識過剰でしょ、傍から見たらベクトルの違う美青年二人がそこらにいる(とりあえず外見と中身は)普通の私に、なんてねぇ。それにホラ、フレンは確かエステルのこと好きなはずだしだってカプワ・ノールで抱きつかれて真っ赤になってたし、ユーリなんかもうどこからどう見てもエステルとカップルだったしってあれ、何だこれ。いやいやいや落ち着いて私、まずそこは忘れよう。そうだ幼なじみとして心配とかそういうことなんだ、ってあれぇぇそうすると無視できない単語がちらほらと……。
どうしても結論が『そこ』にしか行き着かず、熱を持ち出した頬を押さえながら、それでも必死にあるはずないないと首を振る。が、そんな私の努力も空しく。
「お、気づいたっぽいぞ」
「何だかんだと言ってもそこまで鈍くもないし、頭いいからね。僕らがここまで言えばわかってくれるさ」
「―――僕らがの事を愛してることくらいは」
「勿論異性としてね」と、頬に朱をさしつつもニッコリ釘を刺すことも忘れないフレンとほんの少し耳を赤くしながらも不敵に笑うユーリに見下ろされ、私は今度こそ頭の中が真っ白になった。
「そ、え、何の冗談……」
へどもどする私を見て呆れた表情のユーリだったけど、次の瞬間。不意に真剣な……けれど甘さを含ませた低い声色が耳を打つ。
「冗談なわけあるかよ……愛してるぜ、」
「……っ」
耳元で囁かれて言葉が出なくなった私を追い討つかのように、反対側の耳にも優しくて甘ったるい声。
「僕もだよ。ユーリに先を越されてしまったけど……君を愛してる」
「な、な、な、なななな」
「お前が誰を好きなのか、これから好きになるのかは知らないけどな。まぁ、覚悟しろよ?」
「これからは容赦ないからね」
絶対に惚れさせてみせるから、と異口同音の宣戦布告。同時に降ってきた両頬の温もりに、私の意識は一瞬でブラックアウトしたのだった。
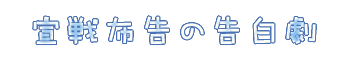
「……流石に一気に詰めすぎたか?」
処理できる限界を超えたのだろう、糸が切れたように動かなくなったを支えながらユーリは苦笑する。「かもね」と同じく苦笑いしながらフレンは同意した。
「それにしても、こっちはずっとを想っていたのに……。まさか、"生い立ちに同情的だから"で片付けられてるとは思いもよらなかったよ……」
「長年の片思いも台無しだな」
を抱き上げながらからかうと、仏頂面のフレンがの体をそっと―――しかし有無を言わさぬ強さで奪った。ユーリは柳眉を僅かに跳ね上げる。
「僕が運んでいくよ」
「なんでだよ」
「を君に抱かせるなんて悔しいじゃないか」
「お前な……」
こんな形でとはいえ告白したことで色々開き直ったらしい。独占欲を前面に押し出したフレンを見て、ユーリは深々とため息をついた。
とりあえず今回は譲っておこう―――次回は俺だかんな、と思いながら。
が何か思いつめている事を、実はユーリもフレンも気づいていた。だと言うのに早々に手を打たなかったのは、彼女が接触を拒むようなオーラを醸し出していたからだった。
長い付き合いの中この状態のに関われた事は一度もなく、また関与を試しても失敗ばかりだった為、拒絶ムードが緩む一瞬を狙っていたというのが本当のところである。
が、それがいつ緩むかも判らなければそのまま放置したらどうなるかもわからない。だからといって自分達二人が近付くのは過去の経験上おそらく失敗するのは目に見えている。
そこで大変不本意ながらレイヴンに協力を頼んだというわけだ。
結果、「ふたりがエステルばっかり守っているのが寂しい(大雑把な要約である)」という可愛いやらもどかしいやらという心情を聞き。安心してもらうついでにそろそろ自分達の感情も意識してもらうか、とこの告白劇になったのだ。
―――その結果、気絶されたわけだが。メンタル強いんだか弱いんだかよくわからんな、とひとしきり苦笑して、―――そしてユーリはその可能性に気づく。
「なぁ、これもしかして起きたときに夢で片付けられたりしないか?」
「………………………それはまずいな」
抱き上げた腕の中で気を失っているを見るフレンはうっすら青ざめた。有り得そうだから困る。
「ま、そんときはそんときでまた言って聞かせてやればいいか」
「そうだね」
歩き出したフレンが、ふと黙り込む。いくらか逡巡した後、穏やかな……それでいて真剣な声でユーリを呼んだ。
「どちらが選ばれても、あるいはどちらも振られても、恨みっこなしだよ、ユーリ」
「……そうだな」
「おっさんも争奪戦に参加しちゃおうかなー」
と木陰からの参戦表明があったとかなんとか。
|