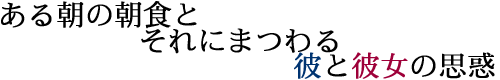鼻をくすぐる美味しそうなお味噌の匂いに誘われるように、瞼が開く。 カーテンの開けられた窓から小春日和を思わせる暖かい陽光が降り注ぎ、ほんの少し舞い上がった埃がきらきらと光り輝いて見えた。 そして、 「おはよ、ちゃん」 お玉片手にキッチンに立つ、大好きな人の笑顔。 「おはよう、レイヴンさん」 それだけで、朝から私は幸せになる。 ギルドと騎士団を掛け持つようになったレイヴンさんは、帝都に居る間は夜から朝までを私の家で過ごす。 狭い家にベッドが二つもあるわけがなく、要するに二人で一つのベッドに入るわけだけど。 世間での「天を射る矢のレイヴン」として培われてきた「女の人好き」という評判に反して、この人はかなりの奥手だった。 ……勿論同じ布団に潜り込むことに変わりないので、時々は深いところまで進むことがあるけれど。 レイヴンさんは私の寝間着の下に手を滑り込ませて肌へ直に触れながら私の胸に顔をうずめるようにして眠ることが多い。時折立場は逆になるが、大体はそうだ。 ちなみに昨夜は、久しぶりに逆転してレイヴンさんにしがみついて眠った気がする。そしてそんな日の朝は、決まってレイヴンさんの手料理が待っているのだ。理由は特にないらしいが、レイヴンさんの作る朝食が好きな私としてはありがたいの一言だ。 まだ覚醒しきらない頭でうすぼんやりとレイヴンさんを見つめる。「ん?」と口元に三日月の弧を描きながら私の様子を伺うレイヴンさんが後ろ手にコンロの火を止めた。 ゆったりとしたシャツの胸元から、心臓魔導器の光がちらりと見える。それは、死を望んだレイヴンさんが生を選びとった証のような気がして、酷く愛おしい。 そんな私の視線に気づいたのか、レイヴンさんは僅かに頬を赤くさせた。 「いやんもうちゃんったら。おっさんのたくましい胸ばっかり見てないでちょうだいよー」 わざとらしく胸元を押さえた、その手の中のお玉に張り付いたタマネギの薄皮がてらりと光る。 お豆腐とタマネギのお味噌汁を作っていたのかな、炊き立てご飯と卵焼きもあるといいな、と朝ごはんの献立を想像しながら、ベッドから降りた私はレイヴンさんの唇にちゅ、と口付けた。 (後は焼き海苔があったら最高だよね) (……焼き海苔があったら……勇気を出して"ちゃん"付けやめて貰える様にお願いしてみよう、かな)
|