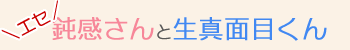「あたし大きくなったらフレンせんせーとケッコンするんだ!」 なんておませさんなことを言いながらスキップしていた4才くらいの女の子を見かけたので、フレン先生に報告することにしました。 「……にしても、フレンが保育園の先生のバイトかぁ」 「似合わないかな?」 水色地の生地に大きいヒヨコが「ぴ」って鳴いているプリントが可愛いエプロンを身に付ける金髪碧眼の美青年、というどこかチグハグな装いのフレンがひとり机に向かって日誌を書き込んでいた。 大学入学後に商店街の一角にある保育園であるバイトを始めてまだ数週間だっていうのに、なんだかベテラン保父さん的なもの……とは違う妙な貫禄を感じるのは気のせいか、いやそんなことはない。 「似合わないというか、保育園の先生なんてユーリのほうがぴったりなような気がして」 「あぁ……本人は否定しそうだけど確かにユーリは割と天職かもしれないね、見た目とのギャップはともかく」 見た目ちょっと目つきが怖くて近寄りにくいお兄さんなユーリは、その実結構な子供好きで、かつ子供受けも良いのでフレンよりはユーリのほうが託児関係の仕事させたらハマり役だと思っている。 対するフレンはどちらかというと先生というよりは教官というか、子供達と和気藹々としているよりは教え導くタイプと言うか要するに、うーん……、 「塾講師?」 「は?」 「えっ、……あ、フレンに似合いそうな職業を考えてたの」 声に出ていたらしく、慌てて説明するとフレンは納得したのかニッコリと微笑んだ。この笑顔が園児たちや保護者のお母さん方に絶大な人気を誇っているのよ、とは彼をアルバイトに採用した初老の女性園長の弁だ。きっと園長もこの王子様のような笑顔に魅入られた一人なんだろうな、と私はこっそり推理している。 外は既に真っ暗で、今夜は月も出ていない。私とフレンのバイト先が目と鼻の先で、ふたり揃って結構遅くまで仕事している所為か、フレンの過保護が炸裂して「僕がバイト終わるまで待ってて欲しい」とシフトが重なる時は半強制的に保育園に寄らされている。 どうもバイトの面接の時に、既にここに寄らされることを了承されていたらしい。初めて訪れたときおっかなびっくりしていた私を、園長さんが「あらあら、あなたがさんね、いらっしゃい」と、全てわかっているのよと言わんばかりのにこにこ笑顔で迎えてくれたときは、妙な気分になったものだ。 何をわかっているのか全くわからないけど、何だかいやに微笑ましげな視線だったのが印象深かった。かと思えば、二回目にお邪魔した時はどことなく悩ましげな視線に加え、「フレンくん頑張ってね、諦めちゃ駄目よ」とフレンに声を掛け、フレンが困ったように曖昧に頷くという、ますますよくわからないことになったけれど、あれは一体何だったんだ。 ちなみにシフトが重ならない日は何故かユーリ(ガテン系のバイトらしい)が私のバイト先まで迎えに来ていて、バイトを始めてから一人で帰宅したことがない現実だったりする。……男衆二人の間で何か取り決めでもあるのかな。何だか申し訳ない気持ちも有るんだけど、実際独りで歩くにはちょっと街灯の少ないところを通ったりして怖いかも、と思っていたのでありがたい。 それはさておき。 「さっきね、ここの園児さんだと思うんだけど」 折角だから報告しておこう、とフレンとケッコンする発言の女の子の事を話す。年上の異性への憧れをとてもかわいらしく思ってのことだったのに、フレンはと言うと。 「……そうか……ふむ……」 顎に手を添え、なにやら難しい顔で考え込んでしまった。何てことはない、幼い子の夢のようなもの…だと思うんだけど、何か気にかかるようなところがあったのか。何かを抑えるように目を伏せ、フレンは重々しく口を開く。 「ちゃんと謝らないといけないな……、気持ちは嬉しいけど結婚出来ないんだって」 「えええ」 なんか思いっきり真面目にとってらっしゃった。昔からこの幼馴染はこんな感じだったなぁと脳裏で溜息をつく。 「ねぇフレン、そんな本気で取り合わなくたっていいと思うよ、小さな子って好きなものや人がころころ変わりそうだしフレンと結婚するっていうのも」 「その子の気持ちは確かに嬉しいけど、」 フレンが緩やかに微笑みながら、やんわり私の言葉を切った。そうして真面目な顔で訝しく思う私の目を覗き込む。 「僕はね、やっぱりそういうものに真摯でありたい。たとえ大きくなった頃に思い出の一つとして数えられるような気持ちだとしても、大人から見たら笑って流されそうな事でもね、ちゃんとこたえてあげる事は大事だと思うんだ」 そう言われて、何の反論も出来なかった。 静かなフレンの言葉には説得力があって、それもそうだなぁと一人納得しかけた時、「それに、」と少し気恥ずかしそうな響きが続いた。え、と思ってフレンを見ると、どこか気まずそうに目を逸らして、それからひとり小さく頷いて目を合わされる。あまりにも真っ直ぐな視線に、思わずどきっと胸が鳴って、だけどなんだか目を逸らしちゃいけないような気がして、フレンの目をじっと見つめ返した。 フレンは一瞬息を呑んで、言葉に詰まったように小さく喉を鳴らし。それから、気持ち普段よりもゆっくりと口を開いた。 「その、僕はには……僕の気持ちとか、潔白さと言うか、そういうものをかけらでも誤解されたくないと言うか……そういうわけなんだ」 「…………」 言われた言葉を何度か反芻して、あぁ、と手を打つ。 「別にフレンがロリコンだとかそんなのかけらも思ってないから、大丈夫だよ」 「えっ、ちょっ」 フレンたら心配性だなぁ、と続けてお手洗いを借りに席を立つ。パタン、とフレンのいる部屋のドアを閉めた向こうから、「そういうことじゃないんだけどな……」と幾分沈んだ声がしたけれど、私は。 「…………思われているんだって、自惚れても、いいのかなぁ……」 気合で抑えた血流が今になって頬を赤く染めていくのを感じながら、イマイチ自信のない確信に情けなく苦笑した。
|