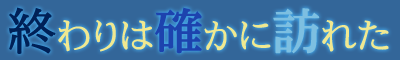オルニオンの夜は静かだ。 急拵えの町とは言え住人の数はそこそこ多いのだが、夜にもなれば北の山に棲みつく動物たちの鳴き声が微かに下りてくるだけになる。 そんな静寂を纏った夜に、凛々の明星の面々が訪れたと報告を受けて僕は彼らが泊まるであろう宿へ一人向かった。 一気に賑やかになった宿のロビーを抜けて、エステリーゼ様やシュヴァーン隊長……レイヴンさんへの挨拶もそこそこに、最愛の幼なじみの姿を探す。 その姿があったのは、宿の裏方……遅い時間の来訪で宿の従業員を気遣ったのだろう、小さなランプ一つだけが灯された仄暗いキッチンで、コンロを借りて暖かい飲み物を作っている彼女の細い背をついに見とめた。 パタパタと忙しなく動くその横顔にははっきりと疲労の色が見て取れる。彼女が術式を使い戦闘に参加し出したと聞いたのはつい数日前のことだ。慣れない緊張ばかりで心身ともに草臥れているはずなのに、人数分のマグカップを用意したり、それぞれの好みに合わせて砂糖やミルクを用意したりと、甲斐甲斐しい。 「」 驚かせないようにそっと背中に声を掛けると、何故か彼女の肩はビクリ、と大きく震えて。 どこか気まずそうに僕に振り返り、 「……こんばんは、フレン」 目を伏せがちにして視線すら合わせようとしない彼女の他人行儀さに、僕の中の何かが燻り出した。 ……また、だ。 この前会ったときも、その前に一緒に魔物と戦った時も。その前も、更に前も、……もうずっと。 は、何故か僕の目を見なくなっていた。緊張と僅かな気まずさと動揺をその身に孕んで、明確に僕との距離を図るようになった。もどかしくも温かかった彼女の柔らかな接触もなくなり、僕らの空気はひどくぎくしゃくしたものに気づけばなっていた。 時折に見つめられる気配を感じるものの、振り向けばそれとなく視線を逸らされて、そのままそそくさと立ち去っていく彼女の背を見送ることだってしばしばあって。 気づかないうちに、に嫌われるようなことをしてしまったのだろうか、そう思い至って、出来る事なら謝りたい、いつものように笑って欲しくて、その度に彼女に会ったのに。……今回もこうして会いに来たのに。 「えっと、あの、ごめん、お湯沸いたから皆に飲み物出してくるね」 ぎこちない笑顔を貼り付け、僕の事を見ないように顔を伏せる彼女へ抱いたのは、焦りと理不尽な怒り。 細い手首を捕らえ、驚いて顔を上げたの視線が真っ直ぐ僕の目を捉えたのにどこか暗い喜びすら感じながら、僕は問うた。 僕は君に、何かしてしまったのかい。 「え……あ、の、フレ……」 戸惑いと焦りを隠さない彼女の瞳に、僕が映る。の瞳の中の僕は、苦しそうに眉根を寄せて何かに耐えるような表情で、真っ直ぐに僕を見返していた。 ああ、僕とは見つめ合っていたのだな―――そんなことに気がついたのは、ロビーに繋がるドアが開いてキッチンに煌々と明るい照明の光と長い影が差し込んできた、そしてがそれに気付いてドアの方に、まるで縋るように視線を向けたその時になってからだ。 「…………よう、フレン」 影―――ユーリは、一瞬僕がを捕らえていたことに息を呑み、けれど瞬きをする間には普段通りの表情で僕らの数歩手前まで歩いてくる。 彼女の横顔から、焦りの色が消えて安堵が広がる。目元が緩み、詰めていた息をやっと吐き出せたような笑みを浮かべたを見て、手首を掴んだままの手から力が抜けた。 「ユーリ」 「悪ぃな、一日の最後に仕事押し付けるみたいになっちまって。……皆大分クタクタみたいだから飲み物持ってってやってくんないか」 「ん、わかった……それじゃ、フレン、…………またね」 辛うじて湯気を立てるマグカップを載せたトレイを持ち上げ、はそそくさと鬱屈したこの空気から逃げてゆく。 またね、の言葉がどこかとってつけたように感じて、僕は細く息を吐いた。 「イラついてんな」 「……ユーリ」 どこか楽しげに、そして僅かに気遣わしげにユーリが笑う。 面白がる響きがまるでに避けられて無様な僕に対する勝ち誇ったものに聞こえてしまい、眉間に力が篭もっていくのを感じて、ぐ、と目を一度強く閉じた。 「……会わなかったうちに、君に大きく水をあけられてしまったみたいだな」 口を突いたのは、いっそ僻みにすら聞こえる愚痴めいたもので、惨めな気持ちになる。 ユーリを見て、心底安心していた。 僕なんかよりも、彼を信頼して、僕に対するぎこちなさはユーリに対しては欠片もなく。 ―――はきっと、ユーリを選んだのだろう。 不自然なまでに距離をとろうとする彼女の態度はそうとしか思えなくて。黒々と濁った感情が胸のうちからどろりと溢れそうになるのをおさえられない。 そのまま僕は、ユーリの反応も聞かないうちに踵を返して裏口から外に出た。これ以上同じ場にいたら、ますますユーリに対して惨めな気持ちになるに違いなかったから。 男の嫉妬なんて醜いものなのだ。わざわざ、そんなものを晒したいとも思わなかった。 「勝負になんて……なりゃしなかったよ」 残ったユーリの呟きなど、聞こえる由もなかった。 自室に戻って、暗澹たる気持ちを抱えて椅子に腰掛ける。全体重をかけるとギ、と軋むその音が自分の今の感情が軋む音に重なって聞こえて、僕は何度目になるかわからない溜息を落とした。 ぼんやりと、窓から夜の闇に染まった外を眺める。 今は、もう何も考えたくなかった。それでも細く差し込んでくる月の光は心の中を見透かすように淡い光を放っている。 ……長い長い片思いだった。彼女を守りたいという願望を抱き、それがどこから来るものなのか考えてを一人の女性として意識している自分を見出して、もう何年も経った。 そんな長い片恋もきっともうすぐ終止符を打たれる。失恋、という形で。 絶対に実るとか、そんな自信はなかった。 下手をしたらずっと一方的に彼女を思ったまま歳を経ていくんじゃないかとも思っていた。がユーリに惹かれていくのだって、当然あり得る……いや、きっとそうなるのではないかという漠然とした予感だってあった。帝都を出てから殆どずっと二人が一緒だったのもあって、尚更。 ただ、それが形になって目の前に現れるという覚悟が出来てなかったのも事実だった。 そしていざそうなって、潔く諦める覚悟も祝福する勇気も出てこなくて、むしろどうしてなんだろうとずるずる引き摺る気持ちと、に対する不条理な怒り……逆恨みに近い思いすら抱くにいたり、自分が相当に女々しい男だったのだと愕然とした気持ちになる。 でも、今夜限りだ。 そんな薄汚い感情を持て余すのは、今夜で終わらせる。 そう決意しても、そんな簡単に今夜で全てに決着なんてつけられるのかと自問自答を繰り返す。眉間の皺が深くなってゆくのを止められもせず、部屋に備え付けの時計を見る。 既に時刻は深夜1時を過ぎ、流石に就寝しないと明日の任務に支障が出そうな時間帯になっていたが、眠気など一向になく、むしろ目は冴えてゆく一方だった。 控えめなノックが室内に響いたのは、無理にでも眠らなければと頭を振ったその刹那。 扉を開けたその前で所在無さげに立っていたのは、だった。 一瞬混乱した。一体何故、こんな時間に。けれど不意にこれで『終わり』なんだろうと感じ取り、ばれない様に小さく息をついてから、どこか不安そうに胸元で手を握り締める彼女に入ってと促す。 椅子を探したものの予備が見つからず、とりあえず僕がさっきまで座っていた椅子に腰掛けるように勧めると、こっちでいいから、と彼女は寝台にすとんと腰を下ろした。そのままの視線はずっと僕に向いたまま。僅かに強張った表情で、話しかける隙を探しているようにも見えた。 「こんな時間に、どうしたんだい?」 元の椅子に腰掛けてこちらから口を開くと、は小さくのどを鳴らした。 緊張で少し血が上っているのだろう、ほんのりと頬を赤らめじっと僕を窺う目は僅かに潤んでいて、この場にそぐわぬ色の欲を感じてしまった僕は思わずごくりとつばを飲み込んだ。 は今しばらく僕を見つめ、何度か口を開きかけて躊躇うことを繰り返し、やがて大きく深呼吸をしてようやく切り出した。 「……その、ね。ユーリにいい加減言って来いって背中押されちゃって」 情けないよね、と眉根を寄せて笑うを、僕は。 気付けば、寝台に押し倒していた。 「………………え……?」 片膝で、状況が把握出来ずに呆然と目を見開くの足を割り、華奢な両手首を全体重かけて寝台へ押さえ込む。 僕はこの期に及んで……彼女が終わりを告げにきたのだとわかっていてもまだ、足掻こうとしている。 それも、間違いなく最悪な形で。 わかっていたのに、の口から今ユーリの名前を聞くのだけは耐えられなかった。 「フレ、ン」 当惑したの呼びかけを受けて、僕はゆっくりと顔を近づけてゆく。近付くにつれて、彼女の髪の甘い匂いが鼻をくすぐり、軽い酩酊感を覚える。心地よさに似た酔いの中、耳元に唇を寄せてささやいた。 「僕は、君が何を言いに来たのかわかってたよ」 告げた途端、目の前の耳がみるみる赤く染まったのが見えた。僕の言葉に素直に反応するが愛おしくて、同時に憎らしく思いながら、続きを口にする。 「君は、……ユーリを選んだんだろう?」 「え……!?」 の声に、強い焦燥感が走った。体を起こしを見下ろすと、何かを間違えておろおろしている子供の顔で僕を真っ直ぐに見上げる彼女の視線とかち合ったけれど、今の僕はただただ漏れ出す自分の感情を載せた言葉が止まらない。 「気付いていたんだ。ここのところずっと、君は僕の事を避け始めていたから」 そうだ、本当に。僕を前のように笑顔で迎えてくれなくなった。気まずそうにちらちらと目を逸らして、僕をちゃんと見ようとしなかった。 「話をしても、どこか緊張してて上の空ですぐ逃げようとする。僕が手を差し伸べてもびくっとして逃げてるみたいで」 「まっ、ちが、違うの」 「そのくせ、ユーリには笑顔で、とても近くて、……どれだけ僕が」 ……嫉妬していたか。 「違う、違うフレン、私……!」 「違わないよ」 「違うの……!!」 の否定を否定し返す。彼女を寝具に縫いとめる腕に更に力が篭もり、足を割る膝を少しずつおし進めながら、これ以上惨めな思いをさせないでくれ、と願う僕の耳に飛び込んできたのは 「フレンが好きなの……!」 思ってもいなかった言葉で。 「…………、は……」 予想外、すぎて、吐息みたいな声が零れた。 手首を押さえつける力が抜けて、がゆっくりと戒めを解いて少しだけ起き上がる。けれど、そのまま逃げたりする素振りはなく、ぎゅうと眉根を寄せたまま近い位置から僕の目を覗き込んできた。その瞳の強さに動揺する僕にお構い無しに、は続けた。 「私が好きなのは、フレンなの。ユーリにはずっと相談に乗ってもらってた」 ずっとフレンのことまともに見られなかったのは、フレンが好きだって気がついた所為で目が合うのが恥ずかしかったからで、フレンに近づいたら気持ちがばれちゃいそうで怖かった、話をしても上の空ですぐ逃げてしまっていたのは傍にいたら胸が苦しくって何にも考えられなくなって、いつものような受け答えが出来そうになくて嫌な思いをさせたくなかったから。 触れられそうになってびっくりしたのは、その途端に真っ赤になって心配かけてしまうかもしれないと思ったから。 半分まくし立てるように言い切られて、僕は呆然とを見つめたまま、その内容を思い返す。 真っ白になった思考回路をどうにか動かせて、吟味して、彼女の言葉の要約を何度も何度も試みて。 ええと、要するに、―――が、僕のことを、好きだから、避けていた、と、言うこと、なんだろうか。 「…………!!」 理解した途端、一気に顔に熱が集まり、更に次の瞬間真っ青になって慌てての上から飛び退いた。 誤解していたとは言え、僕は何てことを……!! 「すっ、すまない……僕は何て乱暴なことを……!」 「私こそ、ごめんなさい。誤解させるようなことしてた……だからお相子、ね」 「……それでも、本当にごめん…」 謝りながら、の前に跪く格好になる。押さえつけた跡が残る手首を恐る恐る取り、己の狼藉を強く恥じながら、もう一度謝罪を口にすると、は困ったように微笑んで「じゃあ、」と繋げた。 「ユーリに嫉妬してくれたの信じてないわけじゃないけど、それでも、もしかしたら自惚れかも知れないから、フレンの声で聞きたいから……告白の、返事、くれたら許してあげる」 少し震える手を伸ばして、の桜色に染まった頬に触れる。 ぴくり、と肩が揺れて反応を示したけれどそれきりで、そのまますんなりと掌に頬を寄せられて、愛おしさと喜びがこみ上げてきた。 「僕も、……僕もが好きだ、もうずっと前から、何年も前からずっと、君の事が好きだよ」 そのまま、まるで吸い寄せられるように。 叶わないと思っていたはずの恋の奇跡に、僅かに唇を戦慄かせながら、唇をそっと重ねた。 そして、翌朝。 眩しい青空の下、凛々の明星一行が出発するのを見送りに来た僕はニヤリと笑うユーリの姿に微妙な罪悪感とそれ以上の嫌な予感を感じた。 「何だよ、時間が時間だから一線越えてくるんじゃねーかと思ったのにそれっぽい素振りねーし」 「………………」 エステリーゼ様やリタ、ジュディスと談笑するを見ながら、ユーリがいやらしい笑みを唇に乗せる。その言葉を受けて思わず頬が熱くなったが、努めて無表情を作り、 「を大事にしたいからね、焦る事なんかないよ。そもそも下世話じゃないかユーリ」 「へーぇ、ありゃどー見ても据え膳だったのにねー! フレンちゃんったら我慢強いのなー」 「ぶげほっ!!」 背後からかかる別の声に盛大に咽ながら振り返って、声の主、レイヴンさんを涙目で睨む。 「ちょっ、……覗いてたんですか……!?」 「いんや、デタラメ。……だけどまぁ、ふーん…………、やっぱり据え膳だったんだねぇ」 ……やられた。 ニマニマとどこか粘っこい笑顔の二人に眉間の皺がきつくなる。このままだとクセになってずっと刻み込まれたままになるのではないかと不安に駆られたけれど、そんな僕の傍へが駆け足で向かってくるのを見てその心配は杞憂だと悟った。 「おはよ、フレン」 「おはよう、。……術式が使えるからって、無理しないように気をつけるんだよ」 頬を染めてふんわりと微笑む彼女に、思わず半分お小言に近い事を言う。苦笑しながらわかった、と返事をするに微笑を返しながら思った。 これはかつて有った日常の一コマで、これから続く僕ら二人の日常になるのだろう。 「一緒には行けないから、ここで君を待ってるよ。……傍で守ってあげたいけれど、今はまだユーリ達に任せる」 ほんの少し、今までは告げられなかった本音を混ぜた言葉と一緒にと向かい合う。 頬に手を伸ばして触れると、くすぐったそうに笑ってから、は行って来るね、と踵を返して女性陣の元に戻っていった。 思わずこみ上げてくる愛しさと寂しさにしばらく無言でたたずんでいると、すぐ傍から忘れていた存在の声がした。 「いやん、目の前でいちゃついちゃって! フレンちゃんってばでれっでれだよ」 「騎士団内でのクールで真面目で優しくも厳しいってイメージぶっ飛んじまうよなぁ、あれじゃ」 「やーでもわかるよね、さっきのちゃん幸せそうでものすっごい可愛かったもんなー、いや羨ましい羨ましい!」 「チャンスはあるぜおっさん。フレンはオルニオンから離れられねーし、俺もおっさんも頑張れば案外横取りいけるかもしんねーよ?」 「まーじーでー!?」 わかりやすい棒読みの挑発じみたからかいに、けれども何と言うか、じわりと本気の気配を感じて、僕は心底思った。 やっぱりついて行かなければ。色んな意味での魔手からを守るために。
|