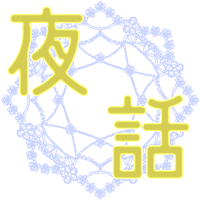気配を感じて目を開けてみたら、何故か金髪の幼なじみに見下ろされていました。 さて状況を整理しよう。 今は夜。 ちらりと横目で窓の外をうかがってみて、それは確かだ。 ここは私の家の寝室。 通常通りの我が家の調度品、仕事で貯めたお金で思い切って買った私好みのランプもきっちり鎮座している。 そして私は、布団にすっぽりもぐりこみ、今の今まで眠っていた。 仕事から帰ってきて、ご飯食べて、湯浴みして、明日の準備を簡単に済ませて、寝た。うん。そうだね、そうしたもんね。 で、フレンは私のベッドに腰掛けて私の寝顔を覗き込むようにしていた。 「……なんで?」 「はは」 思わず漏れ出た疑問の声に、私の顔の両脇に手をついたまま、フレンは情けない笑いをこぼす。 ちなみに「なんで?」の意味は「なんでここにいるの」と「なんで部屋に入れたの」の両方で、フレンの「はは」は多分珍しくも彼が誤魔化したい内容が疑問の答えに含まれているからで。 まぁ、いいか。 あっさり考えることを放棄して、私は相変わらず私を見下ろすフレンを見つめた。 そう言えば、フレンと顔を合わせたのは何日ぶりかな。ふと思い返してみる。 「一ヶ月半ぶりだね、。久しぶり」 そんな私の回想を遮るように、フレンが少し疲れを染み込ませた声で言った。一ヶ月半ぶりか。随分と長い間会わなかったんだ。 よいしょ、と起き上がろうとすると、フレンは少し身じろぎゆっくりと体を起こす。最近トレードマークにもなってきた一般騎士の鎧姿ではなく、こざっぱりとしたシャツと麻のズボンを身につけているフレンを見て、『騎士になる前』のフレンと久しぶりに会ったような気持ちになった。 普通にベッドに座り込む姿勢になった彼は、やっぱり少し疲れた顔で「ごめん」と一言謝ってきた。謝られるようなことをしたのだろうか、と首を傾げそうになって、よくよく考えたらこの一連の状況はそのまま謝罪されてもおかしくない状態だったのに思い至る。けど、フレンのくたびれた様子に既に毒気を抜かれ気味だった私は軽く溜息をついて口元を緩ませるだけにしておいた。 多分、だけど。 フレンは少し行き詰っているんじゃないだろうか。普段のフレンなら、こんな疲れた姿を私に見せたりしない。何せ彼は、品行方正ないじっぱりなのだ。素行不良のいじっぱりであるユーリとは、全く似てないようで根元はそっくりで、ちょっと面白い。 ささ、と軽く身なりを整え―――寝間着を整えてもたかが知れてはいるのだけど、フレンと同じようにベッドに腰掛けると、私は一つ深呼吸。えい、とよくわからない気合を込めて、―――フレンの体(大体胴回り)に抱きついてみた。 「う、わ、わぁ!?」 途端素っ頓狂なフレンの悲鳴。それでも時間帯が深夜であることを覚えていたらしく、しかしかろうじて小声の叫びだったのがフレンらしい。 「ごめんね、いきなり。ただの幼なじみに抱きつかれてもびっくりするだけだよね」 フレンを見上げると。耳まで真っ赤になったフレンが瞬きの存在を忘れたみたいに私を凝視していた。そりゃそうだろう、何の脈絡もなく、本当に突然、しかもこんな接触の仕方なんて大人になってからは一度たりともやってない。 「っ、な、ど、えっと、え!?」 よっぽどの動揺らしく、フレンが発する言葉が全く意味を為してない。この分だと私の言葉は殆ど聞こえてなさそうだ。 触れ合っている部分からガチガチに緊張しているような雰囲気が伝わってきて、抱きついたのは失敗だったかなと思ったけれど、今更離れて普通に話し出すのも妙な気がして、私は抱きついたそのままで、フレンの胸に浸透させる様に、 「お疲れ様」 一言だけ呟いた。 「―――……」 息を呑む気配。こわばっていたフレンの体からゆるりと力が抜けて、その代わり、私の後頭部と背中に恐る恐るといった風情で幼なじみの大きな掌が触れる。 「うん……ありがとう」 そろそろと髪を撫でる感触が忘れていた眠気をゆっくり呼び起こしてゆく。普段どおり、とまでいかないけれど、それでも幾分マシになったフレンの声に安心して、ものの数秒後に私はまた夢に落ちていった。 ―――だから。 フレンが眠ってしまった私の唇、そのすぐ真横に口付けを落としていった、なんて知る由もなくて。 後日昼間に顔を合わせたとき、笑えるほど激しい動揺を見せたフレンに首を傾げることになったのだけど、それはまたいつかの話。
|