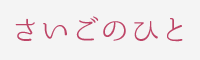※あてんしょん。
深夜のテンションで書き上げて昼間の読み返しで死にそうになるレベルのR18指定鬼灯夢です。
脈絡もなくやるだけやってます。
鬼灯様と秘書殿はすでに恋人関係に変わってます。
コンセプトは「それっぽい言語・局部描写を限りなくゼロに近づけつつそれっぽい雰囲気を出せるかなー?」です
見事失敗しました。
とは言え、濃い描写はしていないつもりなのでもしかしたら描写的にはR15相当かもしれません。
が、やることはがっつりやってます。
描写が予定より薄いだけです。きっと。
しかし書いた本人は恥ずかしくてたまらない状態です。
要するに書いた本人はどMです。
一応ツイッターの夢垢(@dd_sumicco)フォロワ様限定です。(※成人済み限定垢です)
いつもありがとうございます。感謝してもしきれません。
以上、もの凄い保険かけまくりで失礼しました。
年末年始の隙間を縫って何とか出来た時間がどうしてもお暇な時なんかに、適当にお読み下さいませ。
※ 2015.6.23
サイトにて公開開始。
普段着代わりの小袖は、既にずるりと剥かれて衣服としての機能を放棄しており、顕になったほんのり桜色に色づいた本来白いはずの胸板が忙しなく上下している。
その頼りない体のあちこちで歯形や唾液のついた鬱血の痕が存在をアピールしていて、独占欲の表れにしてもそれはいきすぎではないかとは常々思っていたが、つけた当人はこれでも少ないくらいだという主張を曲げることなく飽きもせず次々つけていくので始末におえない。始末におえないけれど、どうしようもないという諦めもある。言ったら聞いてくれる、的な意味では優しいひとじゃない。
「どうでもいいんです、けど」
そんな諦めを隠す気もなく、息の上がった、上ずった声では口を開いた。喉を緩く仰け反らせて、時折びくりと震えてしまうので、体を落ち着けるように努めて規則正しく息をする。背中に触れるひんやりとした感触がそれを手伝ってくれて、うまく落ち着けた、筈だったのだが。
それを視界の端に納めながら、僅かなりとも抵抗を示すの様子に面白く無いと目を眇めた鬼灯は、の中を彷徨わせていた指をぎゅっと折り曲げて、濡れた壁を強く押し上げた。指先に触れるしっとりした温いそこはにとって丁度弱いところで、組み敷かれたままのは途端に飛びはねるような声を上げた。くくく、とそこが痙攣するのと同時に反射的に上げたのであろう両足を、鬼灯は乗り上げていた自分の足と体を使って痛みを感じない程度の絶妙な力でぐっと押さえつける。
もう一度、今度はひっかくように指を動かしてやる。すると短い悲鳴が数度続いて、引きつるような細い息が吐き出された。先ほどの一撃で前後不覚に陥っていたのか、抵抗する術を奪われていたらしいの体から一切の力が抜け落ちる。
あえかな呼吸を繰り返すを見て、彼女の小賢しくも愛しいささやかな抵抗を無力化出来たことに満足して、鬼灯はわずかに目を細めた。が己の手で翻弄される姿を思う存分に堪能したいのに、彼女の理性は随分と強固で中々披露してくれない。だが、その強い理性を消し飛ばし、鬼灯の腕の中で揺れて喘ぐは、あの手この手でなんとしても拝みたいと思うくらいには、魅力あるものだと鬼灯は思っている。―――無論、惚れた欲目も存分に含まれているのは自覚しているが。
「…………っ、も、そういう力技、やめて欲しいって、前に言ったでしょう……」
「いえ、何となく面白くないことを言われそうな気がしたので」
口封じ(性的)とでも呼びますかね、と嘯く鬼灯に、ようやく気を取り戻したは肺の奥からひねり出したような深い溜息をついた。今の指だけで軽く達したせいか、体の奥が微妙に気怠い。
ビリビリと避妊具の封を破る鬼灯を胡乱げに眺めながら、上司兼恋人となった鬼神の勘の良さに心のなかで舌打ちした。無論それすらも気取られてじろりと睨みつけられたが、はあえて無視して続ける。
「……現世だかなんだかで、聞いたんだか、読んだんだか、したんですけどね」
「……さんは今夜はよっぽど酷くされたいようで」
「"男は、女の最初の男になりたがり、女は、男の最後の女になりたがる"」
一段と低くなった声が、ぴたりと止まる。いつぞやかに某神獣に囃し立てられた時よりも更に忌々しいと訴えてくる視線が、珍しく乱れた黒髪の隙間からを捉えているが、当のはやはりそれも華麗にスルーした。
―――いつも負け戦を強いられるのだ。たまには、反撃をさせていただきたい。そう思って、精一杯、妖艶に微笑む。汗ばみ上気した頬と、生理的に浮かんでいた涙で潤む瞳がうまいこと作用して、どうか色気が出ていますようにと間の抜けた事を願いながら、はとろりとぬかるむような視線で鬼灯を捉えた。
「私は、鬼灯様の、最後の、女に、なれるかも、しれませんけど…………鬼灯様は、私の、最初の男には、もうなれません、……ね?」
そして訪れたのは一瞬なのか永遠なのか、わからない静寂。そして、深い溜息と不機嫌なバリトンボイス。
「ええ。……ええ、本当心底忌々しいことに、貴女の全ての初めてを奪えなかった事に非常にムカついてます」
不愉快そうな告白が続く。
「正直、可能なら今からでも千年ちょっと前の貴女の恋人だったとかいうウジ虫野郎を指名手配して拘束して心置きなく呵責しまくってからちょっと頭をフルスイングでぶん殴って貴女に関する記憶の一切を野郎の脳内から綺麗さっぱり消したい、もしくはどこかの青狸……失礼、未来からきた某ネコ型ロボットからタイムマシンを強奪して歴史改変と洒落込みたいぐらいにはムカついてんですよ、これでも。今のところどうしようもないっちゃないんでこうやって貴女を虐めることで憂さ晴らししてますが」
最後に聞き捨てならないことをさらりと告白されたけれど、それに危機感覚えたところで逃げ出せる状態にないは辛うじて動く顔の筋肉を引きつらせながら、目の前のとんでもなくおっかない鬼を見上げた。
そのとんでもなくおっかない鬼こと鬼灯は、どこか急いたような動きで、くったりと転がったまんまのの手を引いて起き上がらせると、すぐ傍にあるそこそこ上質な革張りの椅子に深く腰掛けた。よろめくの腰を両腕でしっかりと抱きかかえ、両手を肩に乗せるように指示すると、の体を脚にまたがらせるように据えて、ゆっくりと腰を下ろさせていく。
質量を持った熱が潤った入り口に触れ、この後どうなるかを大方予想できたは、小さく唾を飲み込んだ。
案の定、予想を違えることもなく、はその熱さに体を震わせる。ただ、つながる事がいつもより妙に性急に感じたのは、気のせいだろうか。
剥き出しの胸が丁度鬼灯の顔の高さになって、それにかこつけてか、鬼灯が膨らみの間に顔をうずめた。鎖骨の真ん中にひやり冷たい鬼灯の角が触れて熱さに喘ぎながら体がブルリと震える。左の膨らみの影に鋭い痛みが走って、また噛まれたとぼんやり思っていると、揺らされることなくただつながったまま、不意に顔をあげた鬼灯に唇を奪われた。微温い舌が唇を割って這いまわり、の舌先をちろちろとくすぐったと思うと、そのまま軽く吸われて、そっと解放される。
「まぁ、貴女が私の最後の女であるのは確かですよ、安心なさい」
「…………べ、別に安心なんて」
唾液に濡れる唇に息を吹きかけるように囁く鬼灯の喉の奥が、くく、と鳴った。
笑われた、そう感じてぷいと顔を逸らした途端に一度だけ揺さぶられて、変な声を上げてしまう。必死に口を噤んで非難を込めて鬼灯を睨みつけてみたが今度はこちらがスルーされた。
「貴女のことは、私が責任持って骨の髄まで遠い未来に貴女が死ぬまで……いや、死んでもですね。―――私に依存させまくりますから、さんはただ覚悟してればいいんです」
「なんですかそれ恐ろしい……く、あっ、ちょっ、んんっ」
鬼の身で死ぬなんて、それこそ後何千、もしかしたら何万年も先の話で、先が知れない。要するにほぼ未来永劫ということだ。
つまりは一生、或いは万が一死んで生まれ変わることがあったとしても。
はこの鬼神を求めつくして、この鬼神に求めつくされる。
いきなり突き上げられて途切れかけた思考が、辛うじてその事実をに刻みつけた。あとはあられもなくあがる悲鳴じみた声を殺そうと必死に唇を噛みしめる。
その唇に、添えるように鬼灯の指が差し出されて、たまらず噛み付いた。強く噛んだせいで牙が軽く指の皮膚を切ったのかほんのりと鉄の味を感じながら、必死に指を噛みしめて、揺れる視界と意識の中でただ只管に鬼灯にしがみつく。
だって、どうしようもなく気持ちいい。どうしようもなく嬉しい。どうしようもなく、鬼灯が愛おしい。だから、こうやって愛されている時だけは、絶対に離れまいと、しがみついた。
濡れた音と鈍い衝突音のようなものと荒い息遣いだけがこの空間を支配していることに、お互いがどうしようもなく昂ぶるのを感じているけれど、自身よりのことを知り尽くしている鬼灯が弱点ばっかり攻めてくるので、結局ばっかりどんどん意識が押し上げられていく。それが悔しくて―――、白んでゆく世界の中で、最後の意趣返しとばかりに、何とか、そこを締め上げると、小さく息が詰まるような声が聞こえて、それを最後に、の世界は白に埋もれた。
「…………本当、貴女はどこまでも私に食らいついてきますねェ」
すっかり気を失ってしまったの体を清めて、身なりを整えてやりながら、鬼灯はうっそりと囁いた。
―――私の、最初の男には、もうなれません、……ね?―――
あのどこか勝ち誇った艶やかな微笑みに、自分ばかりが煽られた。それだけでは飽きたらず、―――の、最後の攻撃は、わずかに余裕を持たせていたはずの鬼灯にとどめをさした。彼女の、そういう負けん気の強さは心地よい。言うつもりはないが、正直なところ負けっぱなしなのは己だと、鬼灯は思っている。
すっかり動かない体を抱きかかえると、それなりの重みが腕にかかったけれど、その重みが愛おしい。そう思える相手はだけだった。
眠るを定位置にそっと座らせてから、鬼灯は換気の為に小窓を開け放った。…………さすがに、いくら二人しかいない深夜の閻魔庁の執務室だからって、ついついいちゃついた挙句、流れで致してしまったのは正直どうかと思わないこともない。とはいえ、とてつもなく背徳的かつスリリングでなかなか(いや実はかなり)よかったのも事実ではあったが。
殆ど片付いていたとはいえ、机の上に押し倒してしまった衝撃で数枚の書類が床に散らかっていた。それを拾い上げ、トントンと揃えて机に片してから、ふと、眠るに囁きかける。
「貴女が、私の最後の女であるのと同様に」
―――私が、貴女の最後の男でなければ、許しませんよ
ううん、と眉間にしわを寄せて唸るに口づけて、鬼灯は退席中の札を外しに扉を開けた。
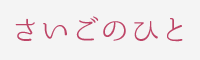 |