「鬼灯様、いい加減になさって下さい」 「……っ」 いつになく怖い顔でが直属の上司を睨めあげていた。怒りが存分に込められた眼差しを受け、珍しく面食らっている鬼灯の頬は、常にない程赤い。 それだけでなく、微かに息も荒い。歩く度に少々ふらついたりもしている。いつもは鋭い目はどことなく虚ろで、まあ要するに、閻魔庁第一補佐官殿は現在、誰がどう見ても具合が悪かった。 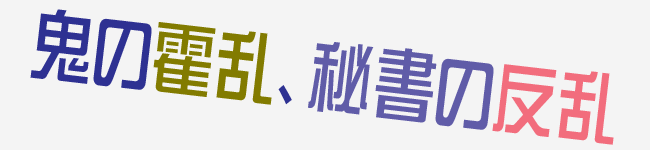 朝の頃は妙に咳払いが多かった。 いつものように裁判に立ち会い、閻魔が亡者の罪状を読み上げる横でちょこちょこ咳払いが挟まるものだから、裁判が終わった後に「鬼灯くん、ワシ何か間違ってた?」と閻魔が恐る恐る部下を伺うほどだった。 「いえ、お見事でした。申し訳ありません、少しばかり喉の調子が悪いようで」 「えっ、大丈夫なの? ワシののど飴あげようか? 美味しいよこれ。舐めるの止まらないくらい!」 「ああだから最近妙に蟻が集っていたわけですね」 「えっうそそれ早く言ってよ鬼灯くん!」 「さ、次の亡者が来ますよ」 「スルー!?」 なんていうやりとりを、書類を運びに来たや小鬼たちが見ていたわけで。毎日遅くまでお仕事されているもんなぁ、と唐瓜が感心する横で茄子がうんうんうううんうんうううん、なんて無駄にリズミカルに頷いていたのだが、からしたらそんな呑気には考えられなかったようだ。 眉をひそめて、しばし上司を観察し、何事かを考えて裁判室を退出。その後何度か同じように書類を運び込む度に、は鬼灯の様子をつぶさに観察していた。 それから、また何度か同じような観察を経て。 「鬼灯様、お体辛いのではないですか? 後は私や他の皆さんとで処理しておきますからもうお休みになって下さい」 本日最後の裁判が結審し、これから執務室に戻って書類をまとめようという時になって、我慢ならなくなったがとうとう鬼灯にそう持ちかけた。最初は咳払い程度だった鬼灯の症状がじわじわと悪化しているのに当の鬼灯本人が素知らぬ顔で仕事を続けようとしたのを見かねたのだ。 「大丈夫です。全く辛く無いといえば嘘になりますが、これくらいなら平気ですよ」 「平気とおっしゃいますが、朝に比べたら随分顔色が悪くなられてます」 「多少の疲れが出ただけです」 でも、と食い下がるの援護射撃に出たのは、 「鬼灯様ー、無理は駄目だよ無理はぁ」 獄卒の異端児、茄子である。馬鹿茄子! と唐瓜は慌てて親友の口をふさいだが、遅かった。眉をひそめる鬼灯に対し、は思わぬ支援を受けて何度も頷いている。更に、 「確かにねぇ。鬼灯くん、声もだいぶ枯れてきてるよね? 喉やられてるんじゃないかなぁ」 閻魔庁トップもの援護に回り出し、唐瓜やほかの獄卒達もおずおずと閻魔の言葉に同意した。 「ね、皆さんもそう仰ってますから。幸い、今夜はそれほど重要な書類も急ぎの報告書もありませんから、鬼灯様がお休みになられても問題ないかと思いますよ」 「……」 言い募るを、鬼灯は無表情で見つめ返す。わかってくれただろうかと固唾を呑んで見守るや閻魔、獄卒たちの期待は、けれど「結構です、これは私の仕事ですから」という一言で無情にも砕け散った。 「強情なんだからぁ、休めばいいのに」と嘆く閻魔の声が届いて、ああやっぱりそう言うと思った、と溜息をつく唐瓜だが、予想はしていても正直あまりいい気分ではない。だって、普段は弱っているところなど全く見せることのない鬼神が、誰が見ても体調不良とわかる程にふらついているのだ。声だって随分出しづらそうにしているし、咳もますますひどくなっているように思う。誰が見たって休養すべきだと断じるだろうに。 そんなことを考えている唐瓜の耳に、パンパンと手を叩く音が響いてはっと我に返る。音がした方を見ると、虚ろになりつつある目を吊り上げて鬼灯が仕事を促していた。 「私の体調なんぞ構わなくて結構です、さあ皆さん、とっとと仕事を片付けますよ」 そう言った直後、ガン! と硬いものに強く衝撃を与えた音が響いて、何事かと全員の注目が集まった先にいたのが近場のテーブルを蹴りつけたで、そして―――冒頭に戻る。 「鬼灯様がするべきお仕事は今即刻この場から立ち去ってご自分のお部屋で体調回復に努めることです。それ以外は私が許しません。今の鬼灯様が執務室へ戻られる事も許可できません。部下が上司に何を、と思われるでしょうが、鬼灯様がご自分の体調を気遣われないのなら、それを気遣うのは秘書である私を始めとした部下一同、そして鬼灯様の上司である閻魔大王です。そしてその私達が、口をそろえて休まれることを進言したのです。どうか賢明なご判断を。もしも書類のことを気にされているのであれば、どうか私達を信じて下さいとしか申し上げられません、が…………言わせて下さい。本当に仕事を進めたいのであれば、まずは体調を整えてから改めて手を付けるほうがよほど効率的でしょう。具合を悪くして鈍った頭で書類仕事をしようなんて、私から言わせていただくとむしろ仕事の失敗を増やすだけの愚策です。鬼灯様のご判断を愚の骨頂だと罵ることしか出来ません。私は鬼灯様の秘書です、貴方の腹心であるべき秘書に、上司を馬鹿にするようなことを言わせないで下さい」 ほとんどノンストップでから飛び出した言葉に、唐瓜や茄子はおろか、閻魔や鬼灯本人まで呆気にとられてしまっていた。流れるように紡がれた内容は、聞いた者を圧倒して反論を許さない。怒りをぶつけたと思えば、仕事の効率化を訴え、その流れで情にも切々と迫り、しまいにはこれだけ言ってもきかないってことは貴方は馬鹿だって言っちゃってもいいんですね、とほぼ脅迫で締める。端から聞けば傲慢な内容だけれど、それを訴えるの声は、どこまでも真摯な響きが揺るがなかった。 「…………わかりました」 はぁ、と深い溜息と一緒に鬼灯が肩をすくめる。「そこまで言われてしまったら、おとなしく休むしかなさそうですね」と続いたそれは、事実上の敗北宣言だ。 件のはというと、ようやくわかってくれたのかと満面の笑顔になり、直後その笑みに緩んだ顔を引き締めて、鬼灯の腕を引く。 「皆さん申し訳ありません、私は鬼灯様をお部屋まで送ってまいりますので、今しばらく業務をお任せします。戻りましたら追って指示を出しますので、どうか戻るまで、よろしくお願い致します。……頑張りましょう!」 裁判室の入り口で頭を下げるとそのを見つめる鬼灯の姿が閉まる扉の後ろに消えて。 「…………すげえな様。あの鬼灯様に有無を言わせず、挙句論破したぞ……」 「案外、鬼灯くんよりもちゃんを怒らせたほうが怖いのかもねぇ………」 獄卒の誰かが呟いた言葉に反応した閻魔の一言が、今この場にいる全員の気持ちを見事に代弁していた。 「……ということも、ありましたっけね」 「…………あれは忘れて下さい」 が真っ赤に染まった顔を両手で必死に隠す。その赤さ具合と言ったら、またも体調を崩してしまった鬼灯よりも更に赤くて、眉間には深く皺が刻まれている。どうやら冗談抜きでの中で黒歴史認定されているらしい。はあいも変わらず、鬼灯が横になっているベッドの傍で「うー」と恥ずかしそうに唸っていた。 「……貴女は、忘れて下さいと言いますが……」 「あっもう鬼灯様、おしゃべりしてないでちゃんと寝て下さい」 咳き込みながら尚も話を続けようとする鬼灯にが慌ててダメ出しをしながら布団を鬼灯の肩の位置まで引き上げた。「ちゃんとお休みにならないと治るものも治せませんよ」と立ち上がったが、妙に壁がボロボロになったところに無理やり備え付けられた感のあるドアを開ける。 ギギィ、と軋んだ音の向こう、の部屋に増築されていた台所からいい匂いがして、そういえばさっきおかゆを作ったとか彼女が言っていたのを思い出す。すぐ持ってきますね、と己のテリトリーに消えていくの背中を見送りながら、鬼灯は体の熱を逃すように熱い息を吐いた。 は忘れろといったけれど、忘れられるわけがない。 ―――体調を持ち直した翌日の執務室で、は頭を下げて待っていた。 「昨日は大変失礼なことを申し上げました。それも、大勢の目がある中で獄卒のトップに立つ方が部下に怒鳴られるなど、本来あってはならないこと。本当に申し訳ありませんでした。…………どのようなお叱りも、受ける所存でございます」 神妙な面持ちで鬼灯を静かに見上げるに、鬼神は静かに首を振ってみせる。 「謝らねばならないのは私です。確かに、昨日は限界が来ていました。それをおしてまで業務に就こうなど、さんの仰る通り逆に仕事を増やすような愚策の中の愚策。…………貴女は私のことを心配してくださったのでしょう? 他の皆さんがいる中で叱られたのも、私には良い薬だったのです」 が鬼灯の為を思って敢えて声を荒らげて怒ったことを、鬼灯は叱られたその場で理解していて。…………そして、自分の為を思ってが怒ったことが、鬼灯は嬉しかったのだ。 鬼灯を恐れて何も言えずにいた他の獄卒の代わりに、彼らの言いたいことの全てを引き受けて、のちに自分が叱責される可能性すらもちゃんと考えて、それでもあの場で言ってくれたのが、嬉しかった。 ただ真っ直ぐに鬼灯の目を見つめてきたその瞳の中には、只管にシンプルな心配という感情と、その奥に灯る怒りと、懇願。 ―――それは、鬼灯にとっては何よりも彼女に愛されている証拠。鬼灯の好意に怯えて、頑なだったあの時のが、その時だけは包み隠さず見せた自分への感情。 それを、当の彼女が忘れてくれと無茶なことを言う。 (全く、誰が忘れるものか) そう、全くもって無茶だ。忘れたくなっても忘れてやるものかと思っていたところに、酷い無茶ぶりをされたのだ。……これは、ちゃんとわからせてやらねばなるまい。 (私が、どれだけ嬉しかったのか、そしてそれを忘れろだなんて、どれだけ無体なことを言ったのか…………その身を以て) そうと決まれば、不調などさっさと治してしまわねばなるまい。鬼灯はもぞりと寝返りを打ち、段々近づいてくるおかゆの香りを待った。 |