「ありゃ、珍しいお客さんだネ」 楽しげにニマァと笑いながら、農園の主である神獣は巨木から音もなく飛び降りた。 実はシロやがここに来る前から酒を煽りつつずっと木の上でのんびり過ごしていたわけだが、彼女たちの存在に今の今まで気づかなかったことから、少しの間酔い潰れていたらしい。そのお陰で大分酔いは冷めているが。 の傍らにしゃがみ込み、様子を確認する。 珍しくしっかり化粧が施されているのに、一箇所だけ舐め取られたように剥げているところがあって、そこから覗く彼女の肌は随分荒れていた。指を伸ばしてちょんとつついてみると、触れた指先にはやはりかさつく感触がある。 ああこりゃ相当お疲れなんだなぁとごくごく簡単な感想を頭の隅に追いやった白澤はもぞりと動き出したに「おっ?」と声を上げた。ちゃん起きるのかなとワクワクしたけれど、残念なことに目を覚ますまでには至らなかったらしい。 は膝を抱え込むように体を丸める。少し冷えるのか、ぎゅーっと体を縮めて。 それもそうだ、いくら温暖な気候だからって外で何も掛けずに眠れるほど今の天国は暖かいというわけではない。 「うーん」 首を左右に巡らせて、にかけてやれそうなものを探すが、この農園に都合よくそんな布地があるわけもなく。辛うじて存在する休憩小屋にだって、そんなものは置いてない。 だが不意に思いついて、白澤はいそいそと、に向かい合うようにして寝転がる。 枕になっている弟子の友はこの際放っておこうと心に決めて、白澤の腕はの腰をゆっくりと抱き寄せた。丸まった分だけ膝が邪魔だけれど、あまり近づきすぎてもあとでびっくりさせるかもしれないから丁度いいと白澤は思う。 自他共に女好きと認める白澤にとって、距離を気にするということはとても珍しいことだった。 柔らかい体を抱き寄せてはふわふわした愛をささやき、女と繋がってその胎内に精を吐く、仕事以外はそんな風にただただ享楽的に過ごすのが常である彼の中で、何故かにだけは父性にも似た庇護欲が湧く。 それが、彼女が自分の好みのど真ん中を貫いているからなのか、それとも彼女が心に深い傷を負っているからか。だが同じように傷を持つ女人はごまんといるし、何人とも関係を持ってきた。好みのど真ん中だからって他の女人と扱いを変えようなんて思ったことは一度たりともない。 けれど現実は明確に、に対してだけ向けられる庇護が存在していて、それが白澤には不思議でならなかった。 (ま、何でもいいんだけどさ。ちゃん可愛いし) ぽんぽんと眠る幼子相手にするように、華奢な背中をリズミカルに優しく叩く。 身近な熱で暖を取ろうとするの体が、ずりずりと白澤の体に近づいてきた。頭を白澤の胸に擦りつけるように体勢を整えるに、服越しとはいえ髪で胸を擽られた白澤は思わず生唾を飲み込む。 に向けた庇護欲求があるのと同時に、を色々めちゃくちゃにしたいという欲求もあるのだから、こればっかりは仕方ないとは思う。―――だが、どうしてもそれをここで全面に押し出すのは何故か辛かった。理由は、豊富な知識を持つ彼にすら、思い当たるようなものはなかった。 本当に、自分でもわからない。 飲み込んだ生唾を思い出さないようにして、白澤は一旦きつく目をつぶる。 次に目を開けた時に飛び込んできたのは、年齢の割にあどけないの寝顔で、それを目にした神獣は何故か急にほっとした。 (なんだろう、ほんと調子狂うよ) 思わず苦く笑いながら、何も知らずに眠るの額にくちづけて。 忘れかけていた酔いに身を委ね、白澤はを暖めるように緩やかに抱きしめたままを追うように夢に落ちた。 (今日は別の夢だけど、いつか僕と一緒の夢を見よう) 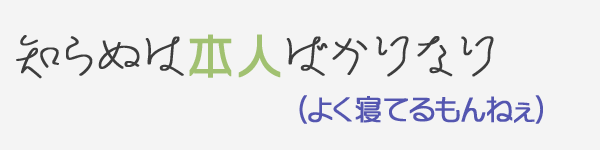 |