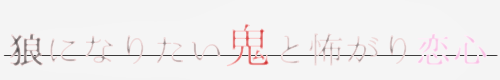「あなたもーおーおかみにぃーかわりーまーすぅかぁー」
彼女自身も判ってはいるのだが、作業に乗ってくると思わずその時の脳内BGMを歌い出してしまうのは実に恥ずかしい癖である。単純作業かつ人気がない時限定、という救いはあるものの、急な来訪者にノリノリで歌っているところを目撃されることの恥ずかしさといったら数日間は布団の中で身悶えられるレベルだったりする。
たとえば、
「あなたがーおーおかみならぁーこわー」「相変わらずさんの選曲のセンスは独特ですね」
「くぬゃああああ!!」
丁度外出から帰ってきた上司に見られたり、とか。
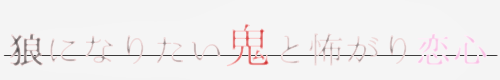 。。。
びっくりして全力で波打つ胸を押さえて振り返ると、鬼灯が自分の席にどかりと座り込むところだった。
深夜と言って差し支えないこの時間まで他部署のトラブル解決に動いていただけあってか、流石に顔色が少し悪い。ふぅと疲れを詰め込んだ長い息をつきながら目頭を指で揉み込む姿に、は恥ずかしさを忘れて慌てて備え付けの流しに駆け込んだ。
急須に手際よく茶葉を入れ、お湯をそそいで数十秒。お盆に載せた湯呑みに適量注いで、鬼灯の机にそっと置く。
「お疲れ様でした」
「ああ、ありがとうございます」
お茶を口にする鬼灯の眉間から、僅かに皺が薄まった。
ふぅ、今度は先ほどと違った空気のため息が聞こえて、ちょっとほっとすると同時にやはり付いていけばよかったかもしれないという後悔が頭を掠める。とはいえ、上司命令で執務室で仕事をするように言いつかってしまったから仕事に忠実でありたいにはこの部屋を出ることは叶わなかっだろう。
「……以前現世に視察に行った際に耳に挟んだんですがね。狼といえば、」
「はい? ……あー」
唐突に飛び込んできた狼という単語に、はぱちくりとまばたきを繰り返して、さっき歌っていた歌詞のことを指しているのかと思い至った。不意に忘れていた羞恥が蘇ってきて、思わず口元を手で覆ったが、
「男は狼とよくいいますが、狼のオスは一生を一夫一妻で終えるほど番を愛し、その求愛行動はかなり長い間続けられます。メスの妊娠中は甲斐甲斐しくメスの面倒を見、出産後は子育てを手伝う習性を持っているんです」
続いた内容はの興味を引くには充分だった。
「へぇ……、予想外に甲斐甲斐しいんですね」
「ええ。まぁ、子育てに関しては群れの他の個体も一緒にするようです。……世の中の男が皆狼だとしたら衆合地獄は今頃閑古鳥が鳴いていたんでしょうが、そうでない現状を省みるに、やはり人間の男は人間でしかなかったわけですね」
確かにと頷きながら、鬼灯が何故こんな話をしているのかにはわからなかった。話そのものは面白いと思ったけれど。
腑に落ちないの様子を見て取ったのか、鬼灯がすっと目を細める。手にした湯呑みを机に置いて立ち上がると真正面に立っていたの隣に並んだ。
「……私は、狼のこの習性の話を聞いた時に、さん」
下ろしていた手を取られて、は思わず鬼灯を見上げる。
「……貴女が求めてくれるのなら―――狼になりたいと、思ったんです」
「―――は?」
一瞬、何を言っているのかわからなかった。
(狼になりたい。鬼灯様が。狼に? 狼。一生番を愛し続ける、メスに甲斐甲斐しいオスの狼。メスに甲斐甲斐しいオスの狼、…………え? で、でも、)
何をいいたいのか、考えが及ばない。ほんの少し正解に近い何かに触れたような気がしたけれど、鬼灯らしくない遠回しな物の言い方に意識を囚われて、掠めた答えに手が届かない。固まったまま思案の海に溺れるを見て、鬼灯が何度目かのため息をついた。
「ああしくじりましたね、やはり遠回しに伝えようなんて柄にも無いことするんじゃなかった……もういい時間です…………そろそろ、仕事も終わりにしましょう」
流石にこの先は業務中にするべきではありませんから。
そう言ってうっすらと笑った鬼灯に目が釘付けになる。それはあまり見たことのない種類の表情で、それを見た瞬間、は何故か捕まってしまったと思った。
「…………、ほお、ずきさま?」
かすれる声で呼んでみても、いつのまにかと向き合って笑みを消した鬼灯からは視線が返ってくるだけで。歌っているところを見られた羞恥によるものとは違う動悸が胸を打ち始めた。
何となく、この先の展開を予想してしまう。
予想して、間違いなく面倒なことになると見当がついてしまったのに、その面倒なことは封じようとしている恋心がずっとずっと待ち望んでいるもので。
聞きたい、言わないで欲しい、聞きたくない、言って欲しい。
分裂しそうな思いが喉の奥で引っかかって気持ち悪くて、顔が歪んでいくのが判ってしまって、見られたくない一心でバッと顔を伏せる。それとほぼ同時に、捕らえられた手が更に強く握りこまれた。逃がさないと、そう知らせるように。
「貴女が、何を思っているのか、何に怯えているか、大体わかります。わかりますが、言いますよ」
頭の上から降ってくる低い声にも、顔をあげられない。この鬼神は、自分のすべてを見通している。どうしても鬼灯への恋心を捨てられない自分も、百年前の二の舞を恐れている自分も、それを知っていて、けれど彼はそれを言い訳に出来ないほどバッサリと、断罪するように告げるのだ。
「私は、貴女が欲しい。以前も言いましたね。さん、私は貴女の身も心も、すべてが欲しいんです。……もっとわかりやすく、あけすけに言った方がいいですか? 貴女を抱いて啼かせて悦ばせて愛でたいと、貴女を脅かすものすべてから守って幸せにしたいと言えば貴女には届くんですか? ―――貴女を愛していると言えば、貴女は私の思いを受け入れてくれるんですか?」
それは決定的な言葉だった。
ただ欲しい、という言葉だけなら。
ただ好意を匂わせてくるだけなら、まだ無理矢理でも誤魔化しがきいたのに。言葉に出来ない嘆きと、叫びだしたいような歓喜が、ぐちゃぐちゃになってを苛む。でもそんな状況にあったのに、の口だけは体と意識から独立したように動き出した。
「―――怖いんです、怖いんです、ただ好きになったひとと親しくしていただけなのに、それを妬まれて、恨まれて、否定されて、仲良くしていた相手から存在をないものとされて、話しかけても汚いものを見るような目で見られるのが」
「知ってます」
「全く関係ない人達の前でたくさんの誰かに囲まれて、殴られて蹴られて、謂れのないことで罵倒されて、角を折られて落とされて、あんな痛い思いをするかもしれないって、あんな屈辱を受けるのかもしれないって、気が狂うと思って」
「そんなことは二度と遭わせないし、させません」
「わかって、いるんです。きっと今の立場を与えられたのは、仕事の手伝いがほしいのも本当でしょうけど、簡単に手を出せないようにする保険の意味もあるんだって、だからそうそう百年前みたいなことにならないのもわかってるんです、でも、鬼灯様」
―――私に、そうまでして守っていただく価値はあるんですか?
「―――そんなもの知りませんよ」
ずっと尋ねてみたかった問いを、それこそばっさりと真っ二つに叩き折られては思わず顔を上げた。鬼灯は不機嫌そうにを見下ろし、歪めた口の端から牙をちらりと覗かせる。
「価値? そんなもの全く馬鹿馬鹿しい。単純に私が貴女を欲しいと思ったから近づいて、貴女を害されて腹が立ったけど直接では貴女にまた危険が及ぶかもしれないから大王経由で報復して、貴女と言葉を交わしたくて百年近く資料室に足を運んで、貴女の傍に居たいから半ば無理やり秘書に仕立てあげた。それだけですよ。そこに価値も何も関係なく、ただ私にとってはさんでなければ要らなかっただけです」
今度こそ、は放心した。
なんて、なんて熱烈な、―――告白。
あまりにも強烈過ぎて、心に蟠っていたものが波のようにじわじわ引いていく。こびりついた恐怖や怯えが完全に消えてしまったわけではないけれど、それでもつい数分前の面倒に思う気持ちはだいぶ鳴りを潜めてしまった。―――嬉しい、と素直に思えてしまった。
知らず、頬に熱が集まってくる。その頬に、ひんやりとした鬼灯の指が触れて、熱の差に酷く狼狽えた。
「う、あ」意味のない声が出て、途方も無い面映ゆさに自由な方の手で何とか顔を隠そうとするが、隠しきれるはずもなく、結局諦める。
「…………鬼灯様って思った以上に情熱的な方だったんですね…………」
「さん限定ですよ」
皮肉ったつもりで呟いた言葉に特大の威力を持った返事が返ってきて、はついに、鬼灯の胸に自分から顔を埋めた。
*** *** ***
きちんと気持ちと感情に整理を付けたい。付けてから、向きあわせて欲しい。
鬼灯にそう伝えて、了承を得たは、鬼灯に手を引かれて自室まで戻ってきた。の部屋は鬼灯によるある種の暴挙で、鬼灯の自室の斜向かいにある。
「送って頂いてありがとうございます、鬼灯様」
「おかまいなく」
自室の戸を半分開けて、はぺこりと頭を下げた。下げた視線の先に、鬼灯の手と繋がったままの自分の手があって。シャットアウトしてきた恋心が全身に行き渡っているのか、それがやたらめったら気恥ずかしい。
耳の先まで熱くなってきて、思わず目を伏せると、頭の上から深い溜息が降ってきた。
「さん」
呼ばれて、慌てて顔を見上げて返事を返そうとして、繋いだままの手を力いっぱい引きよせられた。え、と思う間もなく、腰を抱かれ、―――唇を塞がれる。
最初はついばむように。それから、少し冷たい唇に二度三度自分のそれを甘咬みされたり、舌先で擽るように舐められる。いきなりの口吻に呆然とするばかりで、何を促されているのかわからない。ただただ、まるでのしかかられるように抱き込まれて、のけぞってしまう体勢がかなり苦しい。その苦しさをどうにか緩和しようとして思わず口を開けると、そこにぬるりと鬼灯の舌が入り込んできた。余計苦しくて、「ん、ふ」なんて吐息とも声ともつかないものが出る。
舌を舌で擽られるという、が今までまともに経験したことのない感覚が背筋をぞわりと痺れさせて、掴まれていない方の手で無意識に鬼灯の胸を叩いた。
それに気づいてくれたらしい鬼灯が、おもむろにを解放する。唇が離れる時に唾液がつぅーっと糸を引いているを見てしまったは、恥ずかしさで何も言えずに下を向く。
「すみません、ついムラっときました」
しれっと言い渡されて、鬼灯様! と抗議の声を上げるとあまり気持ちのこもってない声で再び「すみません」と返ってきた。
「狼になりたいと言いはしましたが、流石に送り狼になる気はありませんよ。まぁ……、今くらいのは遠慮なくするつもりですけどね」
とんでもない宣告をされて、は挨拶も何も言わないまま、自室に飛び込んだ。
|