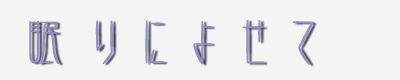三徹めにもなれば誰だってこうなるわよね。第一補佐官秘書は思わず苦笑した。 毎年恒例の今の時期、やはり毎度のように大量の亡者がいっぺんに地獄に流入してきた。地獄全体が繁忙期に突入すると、各庁トップはそれこそ休みという単語がその脳裏から消失することになる。 閻魔庁も御多分に漏れず、閻魔大王も鬼灯もも、ほぼ不眠不休で対応に追われた。 食事も執務室までデリバリー、交代で休憩を取る時間すら惜しい。この期間だけ生活の基盤が執務室になるのがどうにもいけないと、かつて資料室に来た鬼灯がぼやいていたが、なるほどこれはそう愚痴もこぼしたくなると最初の一日のうちに体感させられただった。 そんな、自室に戻れない二週間を経て今朝ようやくピークが過ぎたのを実感した鬼灯が「まずはゆっくり体を伸ばしてきて下さい」とを休憩に出してくれたのが二十分ほど前。ありがたく体を動かしに行ったものの、鬼灯の激務を間近で見ていた身としては、ありがたさよりも鬼灯を心配する気持ちが勝ってしまって、一時間の休憩をさっさと切り上げお茶を淹れて戻ってみたら、件の上司は椅子の背もたれに寄りかかっている。微動だにしない鬼灯の頭は下を向いて、鋭すぎる三白眼は目蓋で隠れて見えなくなっていた。 自分の机にお茶を置いてから、なるべく足音を立てないよう、おもむろに近づく。途中机がガタリと鳴った音にびくついたけれど、鬼灯が目を覚ました様子はなかった。そういえば、ルリオが「鬼灯様は爆睡型らしくて、ちょっとやそっとの音じゃ目を覚まさない」と言ってたことを思い出して、安堵の息をついた。 「…………」 鬼灯の傍で膝立ちして、はそっと鬼灯の顔を伺ってみる。 刻まれていた眉間の皺は、眠っているときは流石に消え失せるらしい。 それがないだけで相当無防備に見える寝顔は見たことのないものだったから、変な胸の苦しさを覚えて急激に顔が熱くなってくる。前から思っていたけど睫毛長いなぁ、とか鼻筋通ってるなぁ、とか起きている時には絶対にできないくらいにつぶさに観察していて、気づいた。 ここ数日のハードワークのせいか、目の下にはくっきりと隈ができている。それもそうだ、裁判の場にも立ち、各地獄で問題が起これば現地に向かい指示を出し、戻れば書類の山との戦いもこなす。そのせいで三徹もしているわけだから。 は立ち上がり、執務室の外へ出た。流石に鬼灯の部屋に勝手に入るのは憚られるので、自室から軽いタオルケットを持ち出して、帰りしなに執務室の入り口に退席中の札をかけて入口の戸を閉める。 部屋を出た時と変わらない鬼灯の様子に思わず微笑んで、ゆっくりと近寄り、鬼灯の肩からくるむようにタオルケットを掛けた。大きさどうかな、と心配していたけれど意外と大きかったのかがっしりした男性の体でも余すことなく覆ってくれている。よかった、と胸を撫で下ろして。 不意に、唐突に。触れてみたくなった。 慎重に指を伸ばし、眠る鬼灯の顔を指先だけで撫でる。そっと顎をたどってみると微かに生える無精髭のチクチクした感触を指に覚えて何だかくすぐったい。一度指を離して、鬼灯の目元へ。隈ができている涙袋の部分をやはり指先だけで出来る限り優しく触れてみた。 触れながら、はもしもを考える。 もしも百年前、嫌がらせもいじめも何事も無くて、鬼灯の気持ちを何の衒いもなく受け入れていたら。 もしも、自分の気持に素直に振る舞えていたなら。 鬼灯様が好きです、と、誰に憚ることなく伝えられたら。 あの頃から好きだったのに。 今だって好きなのに、一度傷ついて恐怖を覚えてしまった心が拒絶する。 またあんな目に遭ったらどうする。今度こそはそれに負けてしまったら、そうしたら鬼灯の傍に居られなくなるかもしれないのに。 それなら、気持ちに蓋をして、こうやって鬼灯を傍で支えていればいい。 恋愛感情なんて、ないものとして。 それなら、”仕事だから”堂々と傍に居られる。 を求めてくれる鬼灯にとても失礼なことをしていると充分にわかっているけれど、にはその選択肢しか選べない。 鬼灯に触れていた指は、いつの間にか無意識に自分の頭右部分に触れていた。そこにあったものは、今は影も形もなくなっている。 「酷いなぁ、私は」 そう、ぽつりと。自分を嘲って。細く息を吐きだし、名残惜しさを感じながら、そっと鬼灯のそばを離れる。 鬼灯が目を覚まさないうちにある程度書類を片付けてしまおうと自分の席に戻ったものの、やはり同じく三徹していたにも限界が来ていたらしい。椅子に座るんじゃなかった、なんて無茶な愚痴を頭のなかで吐いたのを最後に、意識が闇に落ちた。
|